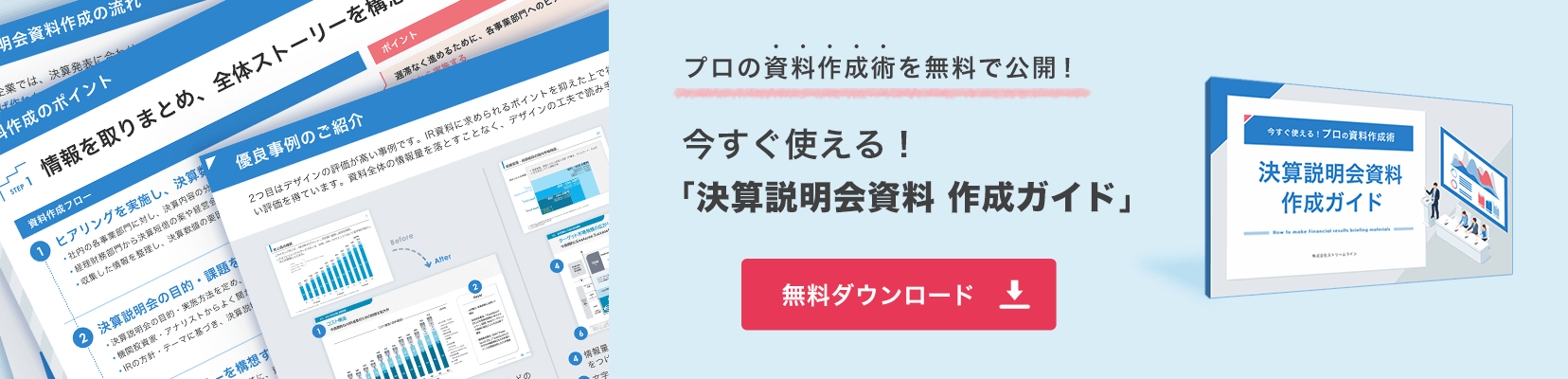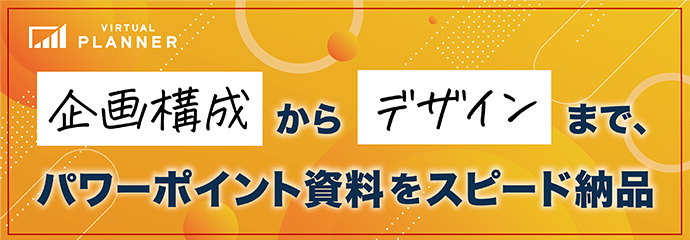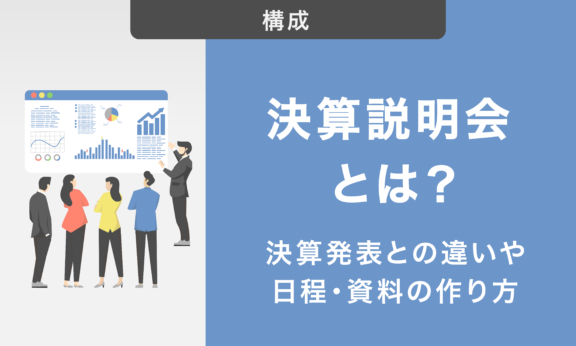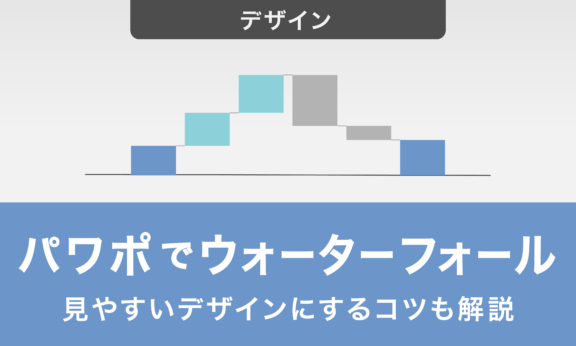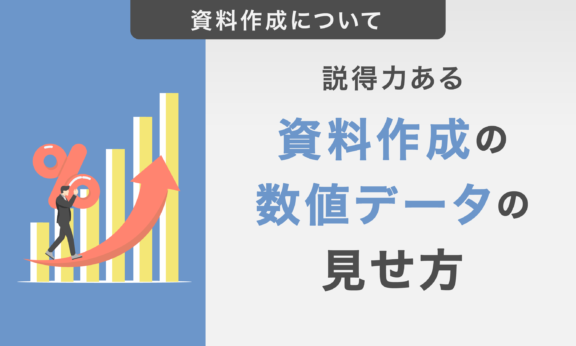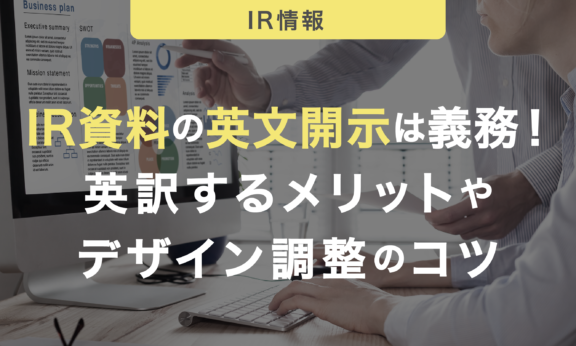文章推敲のチェックポイント【作成編➄】読みやすいリズムを生む3つのポイント

今回は、文章を推敲する際のチェックポイントのご紹介です。自分の文章ならまだしも、他人の文章を推敲する作業は時間を要します。文章推敲を行う際には、正確性やスピードの向上を図るために、あらかじめチェックポイントを明確にしておくことをおすすめします。
今回は「リズム」のチェックポイントです。
今回は、文章推敲シリーズの最終回です。
第1弾「文章を短くする」、第2弾「正しい文法にする」、第3弾「適切な言葉使いをする」、第4弾「表記ゆれを解消する」として、文章推敲のチェックポイントをご紹介してきました。
最終回の第5弾は「見た目やリズムを調整する」です。 ビジネス資料の読みやすさの向上のために、文章の見た目やリズムを調整するコツをご紹介します。
自分で読んでみて読みやすいと感じるレベルまで、文章の見た目やリズムを引き上げましょう。
1.読点を正しく打っているか
読点(、)の位置は文章の読みやすさに大きく影響します。
読点を適切な位置に打つことで、読みやすいリズムが生まれるためです。
以下に読点の打ち方のルールをまとめます。
原則読点を打つ箇所
・接続助詞の後
例:商談数は増えたが、業績には繋がらなかった。
・長い主語の後
例:5年前に取引していた業者が、先月買収された。
・条件や理由、原因を示す語句の後
例:大型案件を受注したので、今期は業績が良い。
・時間や場面が変わる箇所
例:苦情を受け容れたところ、お客様の態度が急に変わった。
・複数の情報を並列的に並べる箇所
例:経理と人事、法務、総務、経営企画は一つの部門にまとめる。
・ひらがなや漢字が続いて読みにくい時
例:今後、事業構造改革の必要性が高まる会社が多い。
・独立語の後
例:はい、必要ありません。
・カギ括弧の代わり
例:データの蓄積がカギになる、と経営者は主張した。
また、文頭の1語目にはなるべく読点を打たないこともポイントです。
悪い例
・さらに、その施策では潜在顧客への認知拡大も実現した。
良い例
・さらにその施策では、潜在顧客への認知拡大も実現した。
いかがでしょうか。読点の位置次第で読みやすさが変わることが伝わりましたでしょうか。
適切な位置に読点が打たれている文章は、リズムも見た目も気持ちが良いものです。
2.括弧を使い過ぎていないか
次は丸括弧やカギ括弧などの括弧の使い方です。
括弧を使いすぎると強調や補足で溢れてしまい、情報の優劣が曖昧になり、文章がわかりにくくなります。
単純に文章としての見た目も悪くなります。
悪い例
・「吉野家」と「はなまるうどん」と「ガスト」が協力する、共通割引券【3社合同定期券】の“日経新聞”のリリース『共通割引券で相互送客へ』が出ている。
良い例
・吉野家とはなまるうどんとガストが協力する、共通割引券「3社合同定期券」の日経新聞のリリース“共通割引券で相互送客へ“が出ている。
上記は極端な例ですが、括弧は最小限に留めるようにしましょう。
3.情報の羅列は箇条書きにしているか
営業資料や企画書、講演資料、決算説明会資料などのビジネス資料はいわゆる読み物ではないため、長々と文章を繋げていくのではなく、情報を簡潔にまとめていくことが求められます。
複数の情報を羅列する場合は、なるべく一つの文章ではなく、箇条書きにして一覧で見せるようにしてください。
箇条書きは情報の構造を視覚的に捉えやすく、文章よりも理解のスピードが早まります。
悪い例
・オンラインで商談をすることで、営業マンの移動時間の短縮や商談の密度の向上、商談数の増加、営業活動の可視化などを実現することができます。
良い例
・オンライン商談で実現できること
-営業マンの移動時間の短縮
-商談の密度の向上
-商談数の増加
-営業活動の可視化
これだけで見た目もリズムも全然違うものになります。
以上で文章推敲のチェックポイントのご紹介は終了です。
文章の推敲に費やす時間は少ないに越したことがありません。ぜひご紹介したポイントを会得してください。