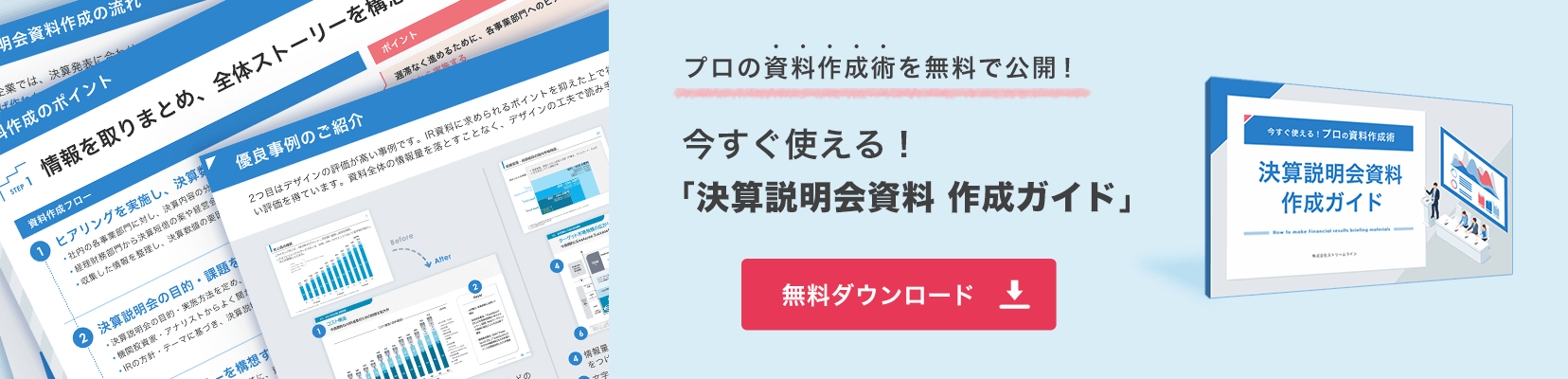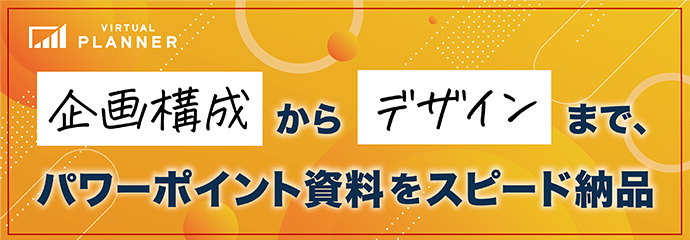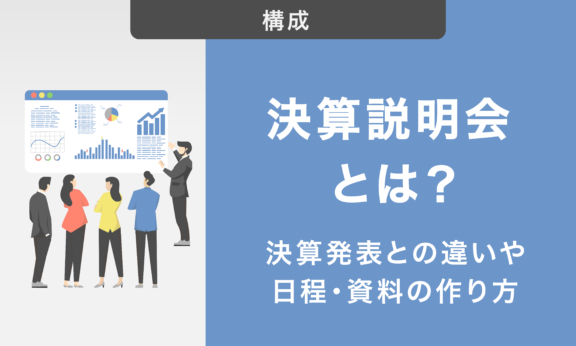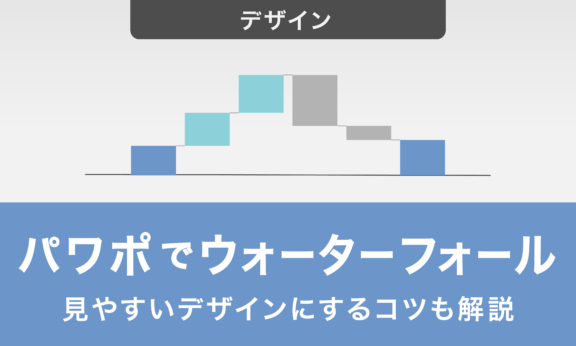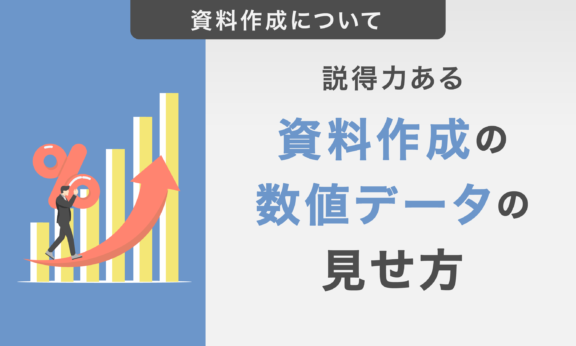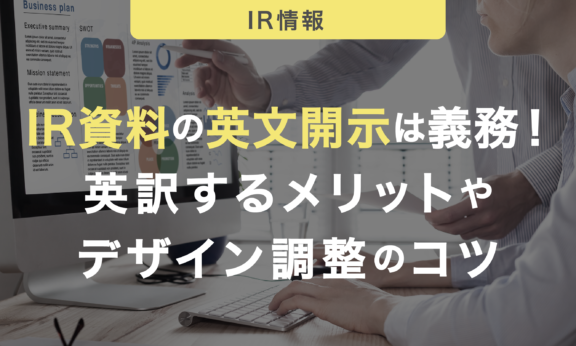成果を出す営業資料の作り方|読み手・態度変容プロセスの理解【作成編③】

営業で成果を出すためには、資料もぬかりなく準備する必要があります。今回は、読み手の解像度を上げる態度変容プロセスに焦点をあてて解説します。
今回は、成果を出す営業資料の作り方【作成編③】のご紹介です。
1.こんな方におすすめ
成果を出す営業資料の作り方シリーズでは、お客様からのご期待をいただける営業資料とはどのようなものか?を考察し、実際に作るにあたって押さえておくべきポイントを解説します。
このシリーズ記事を読んでほしい方は下記のような皆様です。
・社内で見よう見まねで営業資料を作っているが、お客様にとってわかりやすいものかわからない・・・
・個々の社員がばらばらに資料を作るため統一感がない・・・
・そもそも商談が苦手・・・
・営業資料をしっかり準備せず口頭で営業している・・・
・対面時にはいい雰囲気で終わるのに、クロージングがうまくいかない・・・
・自分は営業が得意だったが、部下は営業が苦手で売上をあげてこない・・・
本記事では、「営業資料のページの中身はどのように作成するべきか?」ということについて紹介していきます。
2.営業資料作成のポイント:読み手の理解や態度変容のプロセスを想定する
成果を出す営業資料の作り方|条件把握・ページネーション【作成編②】では、営業資料の制約条件を想定し、ページネーションを検討する手順について紹介しました。
ページネーションの検討といっても、中身を作る段階で最適なページネーションが改めて見えてくるものなので、ここで検討したページネーションはあくまで仮のページネーションとなります。
まずはこの仮のページネーションの状態のまま、ページの中身の検討に入っていきましょう。
中身を検討する上で大切なことは、読み手の理解や態度変容のプロセスを想定することです。
成果を出す営業資料の作り方【作成編②】で策定したページネーションを例に取りながら解説していきましょう。
会社概要(あなたたちは誰なのか?への回答)
↓
クライアントの抱える課題
↓
課題を取り巻く環境(なぜ話を聞く必要があるのか?への回答)
↓
サービスの概要(あなたたちは何を提供できるのか?への回答)
↓
サービスの特長
↓
導入実績(他ではなくあなたたちを選ぶ理由は何なのか?への回答)
↓
料金(サービスの提供を受けるには何をすればいいのか?への回答)
↓
ご利用の流れ・申込方法
ここで、読み手の理解や態度変容のプロセスはどのようになるでしょうか?
・会社概要
読み手の考え例:
A事業だけではなくB事業もやっているのか・・・そちらでも相談できそうだな・・
こういう特許取っている会社なのか・・・独自性のあるサービスを提供しているな・・
社員数こんなにいるのか・・・かなり成長している会社なんだな・・・
競合のA社とも取引がある会社なのか・・・業界について精通しているようだ・・・
→あなたの会社に対する理解や期待を醸成
・クライアントの抱える課題
読み手の考え例:
自社の課題を理解してもらっている・・・
目を背けていたけどこういうことは起きていそうだな・・・
この会社はこの分野の課題解決を得意としているようだ・・・
→課題の共感を促し、課題を再認識させる
・課題を取り巻く環境
読み手の考え例:
外部環境の変化に対応しなければならない・・・
定量データが示す通り、深刻な課題のようだ・・・
→課題への危機感を醸成し、解決への意欲を高める
・サービスの概要
読み手の考え例:
こういうサービスをやっているのか・・・
これなら自社の課題を解決できるかもしれない・・
→サービスの概要を理解させ、興味を喚起する
・サービスの特長
読み手の考え例:
他社にはない特長をもっているようだ・・・
自社にとって導入メリットがあるようだ・・・
→メリットを具体的に想起させ、導入への意欲を喚起する
・導入実績
読み手の考え例:
成果を出しているサービスのようだ・・・
自社もこのような恩恵を受けたい・・・
自社と同じ業種の企業も導入しており、遅れをとっている・・・
→成果に対する信頼を醸成し、具体的な行動を喚起
・料金
読み手の考え例:
この予算なら十分な費用対効果が得られそうだ・・・?
予算を確保し、●月の会議で提案しなければ間に合わない・・・
上司を説得しなければならなそうだ・・・
→ネクストアクションとボトルネックを想定させる
または
→導入のハードルを低く感じさせる
・ご利用の流れ・申込方法
読み手の考え例:
導入にあたって準備が必要そうだ・・・
こちらの手間がかからないため、すぐにでも導入できそうだ・・・
協力メンバーに報告する必要がありそうだ・・・
→ネクストアクションとボトルネックを想定させる
または
→導入のハードルを低く感じさせる
このような感じです。
読み手の理解や態度変容は、こちらが与える情報と与える順番から形成することができます。
読み手に想起してほしい考えを導くように、情報を配置していけばよいのです。
逆に、配置をうまく行ったとしても、「内容がぼんやりしている」など、不十分な情報量・情報の粒度では読み手の態度変容には至らない可能性が高いため、書くべき内容がクライアントの心を動かすか?ということは必ず確認しましょう。