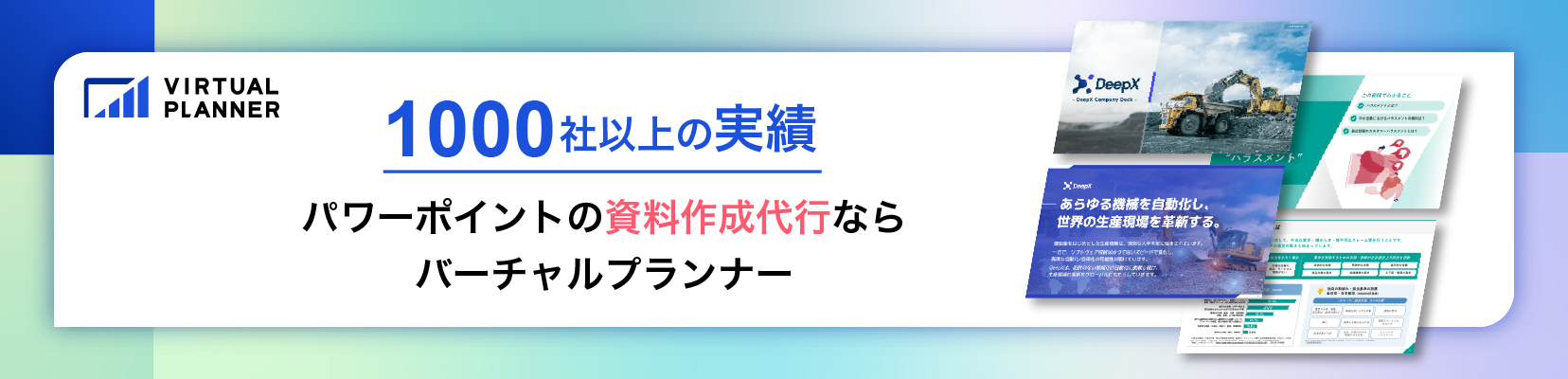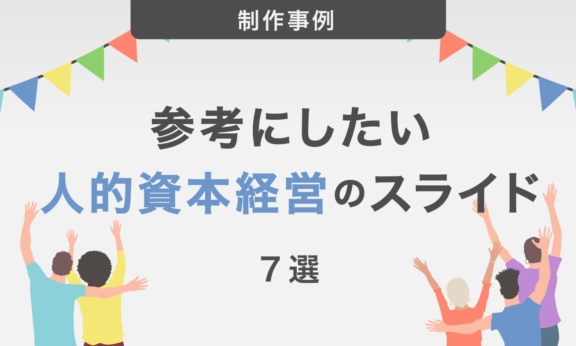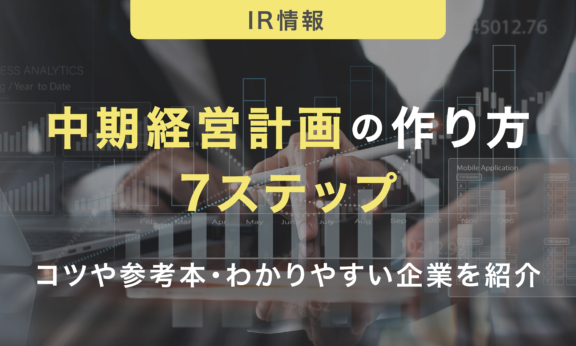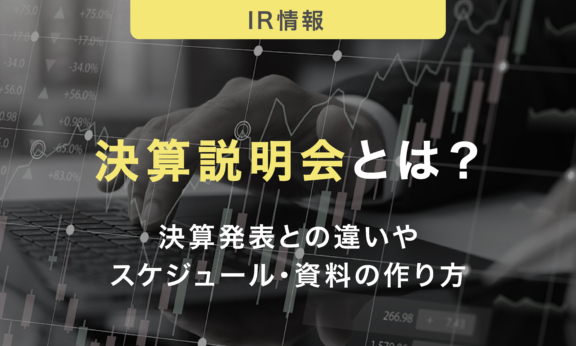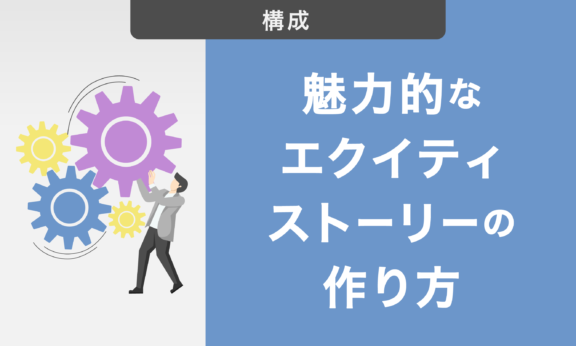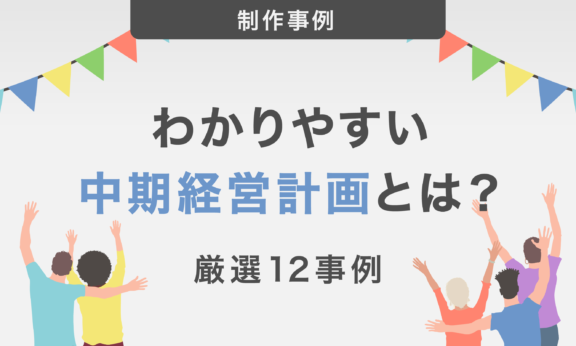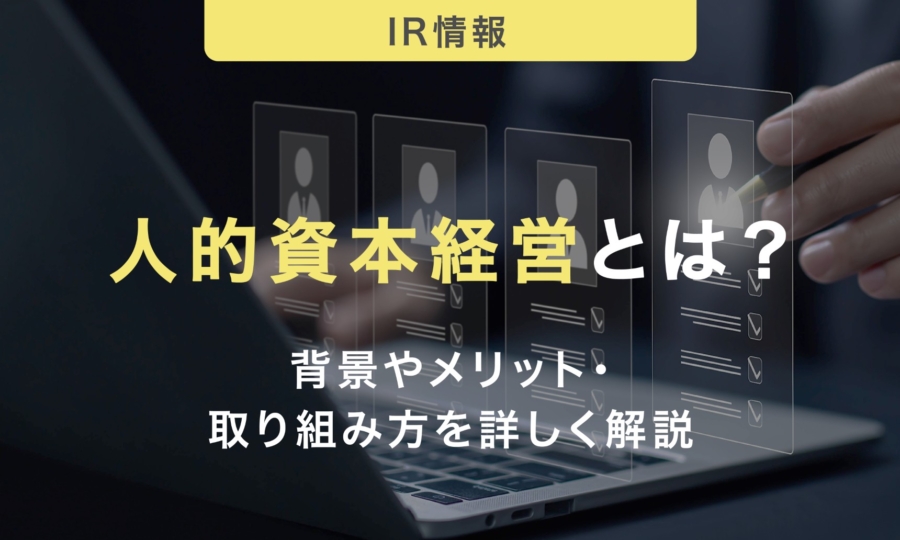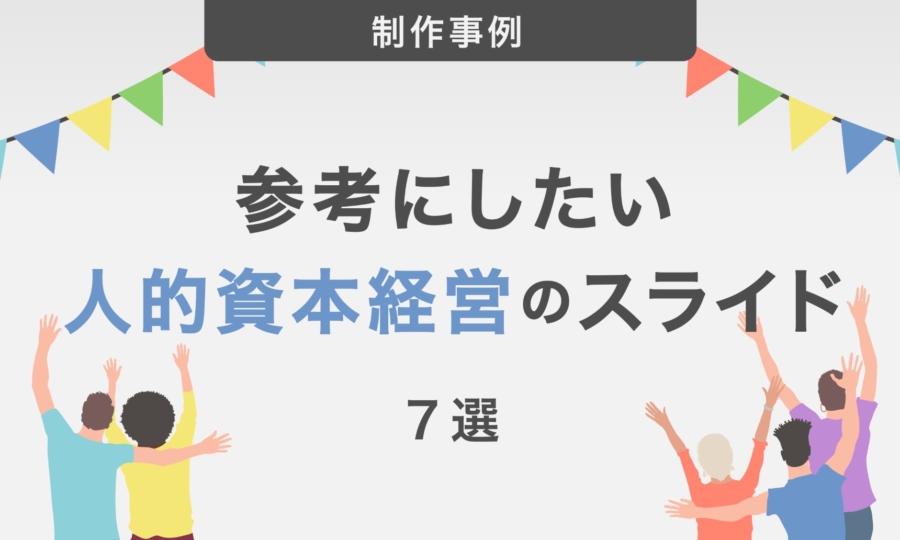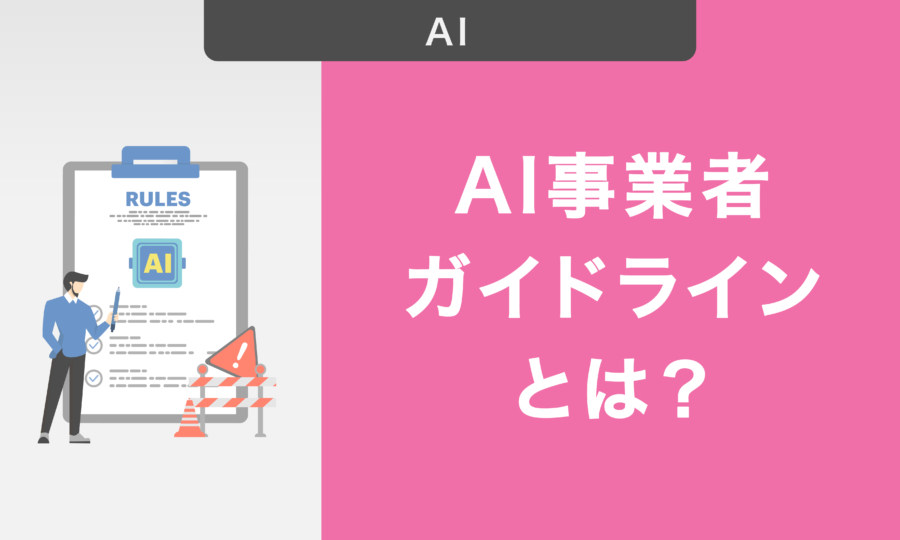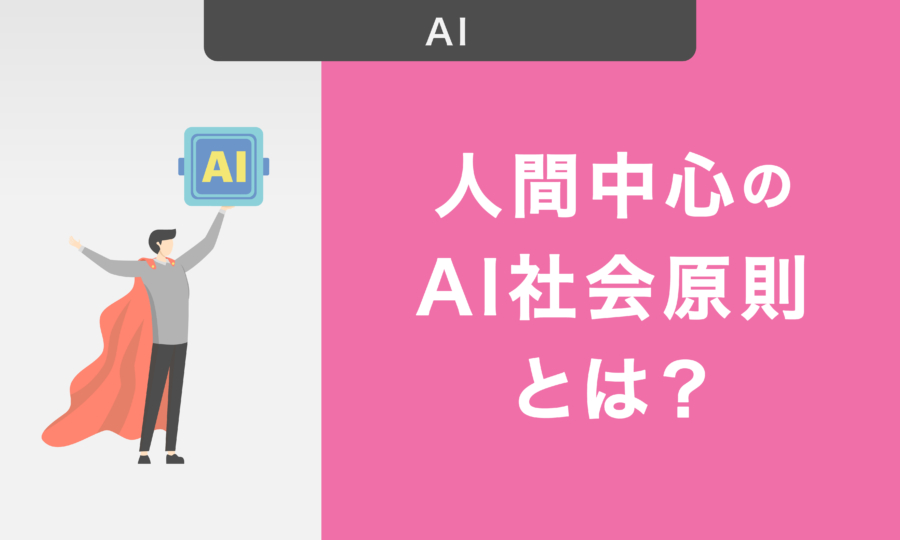【簡単】企画書の書き方を解説!作り方のポイントやテンプレート・具体例を紹介
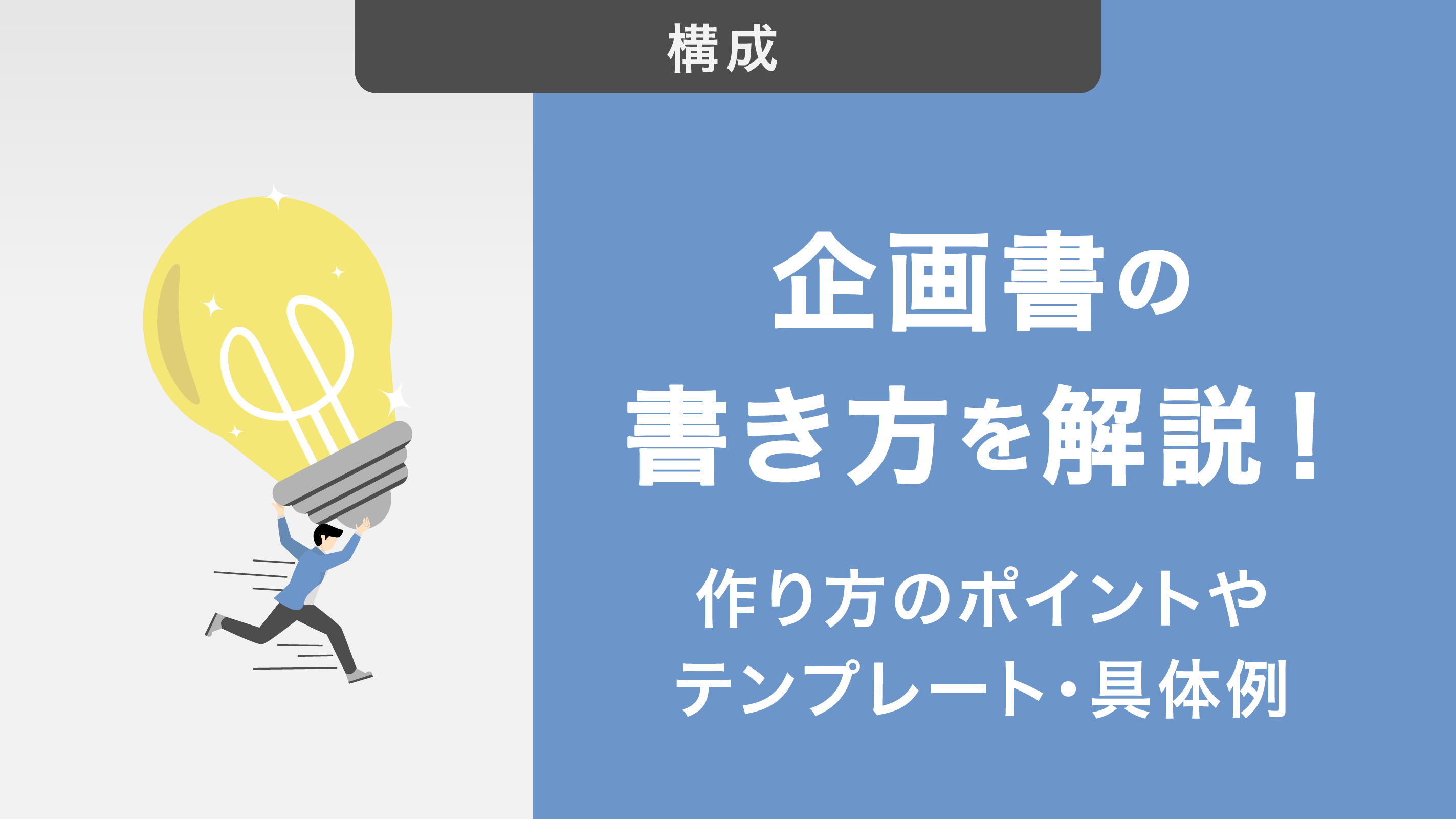
企画書の目的は、企画内容や得られる成果、必要なリソースなどを読み手に理解してもらい企画を採用してもらうことです。また、採用された際にメンバーへ実行計画を周知する際にも使用します。企画書作成で抑えるべきポイントに加えて、参考になるフレームワークや構成例を紹介します。
目次
・企画書とは
1. 企画書を書く目的
2. ビジネスにおける企画書の重要性
3. 企画書と提案書の違い
・企画書の書き方を7つの要素に分けて解説
1. 表紙
2. 現状の分析・企画背景
3. 企画のコンセプト
4. 企画を実施するメリット・デメリット
5. 運営体制
6. スケジュール
7. 会社概要・問い合わせ先
・企画書を書くときに役立つフレームワーク
1. 6W2H
2. CTPT
3. 3C分析
4. SWOT分析
・企画書を書く際のポイント
1. フレームワークを活用して抜け漏れをなくす
2. いきなりスライド作成に着手しない
3. 伝わりやすいデザインを心がける
4. 数値目標を提示する
・企画書を書く際に参考になるテンプレート
・企画書の書き方における具体例
・書き方を押さえてわかりやすい企画書を作成しよう!
企画書とは
まず、企画書の概要について解説します。
- 企画書を書く目的
- ビジネスにおける企画書の重要性
- 企画書と提案書の違い
1. 企画書を書く目的
企画書は新しい事業やプロジェクトを提案し、社内外の関係者にプロジェクトについての理解を得るために作成する文書です。社内の意思決定者にプロジェクトの価値を伝え、承認を得るために企画書は作られます。
具体的には、プロジェクトに会社の人的リソースを割り当てることや予算を確保することなどが挙げられます。予算や人員・スケジュールなどの必要なリソースを明確にし、プロジェクトの実行計画を明確に示せれば、企画を実行する正当性に説得力が生まれるでしょう。
プロジェクトの関係者間で情報を共有し、コミュニケーションを円滑にするためにもわかりやすい企画書を作成することはビジネスにおいて重要です。
2. ビジネスにおける企画書の重要性
企画書は、ビジネスの成功に直結する重要な文書です。新規事業の立ち上げや既存事業の改善提案など、さまざまな場面で企画書が活用されます。
事業の目的や目標・実行計画を明確にし、プロジェクトの方向性を定める指針を示すことが求められます。説得力のある企画書を作成できれば、ステークホルダーの理解と協力を得やすくなるでしょう。
企画書の内容は事業の成否に大きな影響を与える可能性があるため、作成するにあたっては入念な準備や推敲が必要です。
3. 企画書と提案書の違い
企画書と似た資料に提案書がありますが、違いについての厳密な定義はありません。業界や企業によって使い分け方が異なりますが、よくある使い分けの例は以下のとおりです。
| 企画書 | 新しいサービスの内容や企画の実行計画を具体的に紹介する資料 |
| 提案書 | 課題を解決するための方向性を提案する資料 |
企画書は事業の背景や目的、実行計画などを詳細に説明するのに対し、提案書は顧客のニーズや課題解決など大まかな方向性を示すことに焦点を当てた資料のことを指す場合がほとんどです。
企画書の書き方を7つの要素に分けて解説
次に、企画書の書き方を7つの要素に分けて解説します。
- 表紙
- 現状の分析・企画背景
- 企画のコンセプト
- 企画を実施するメリット・デメリット
- 運営体制
- スケジュール
- 会社概要・問い合わせ先
各要素に盛り込むべき内容を精査すれば、自然にクオリティの高い企画書ができあがるでしょう。
1. 表紙
表紙では、企画の概要を端的に伝えます。具体的には、企画名・提案者名・提案日などの基本情報を明記します。
とくに企画名は企画書を読む際に真っ先に目に入る部分であるため、プロジェクトの主旨を一目で理解できるような、インパクトのあるタイトルを付けることが大切です。
必要に応じてイメージ画像を使い、視覚的にアピールできるとなお良いでしょう。シンプルかつ明快なデザインを心がけ、読み手に好印象を与えるよう工夫することが大切です。
2. 現状の分析・企画背景
現状の分析・企画背景では、企画の背景となる現状の問題点や課題を明確に示します。
現状の問題点や市場の動向・競合他社の状況などの企画を取り巻く環境を分析し、客観的なデータや事例を用いて現状分析の根拠を示しましょう。
現状分析を通じて、企画の必要性や重要性を訴求できると読者の興味を惹きつけられます。読み手が企画の背景を理解し、共感できるような内容にまとめましょう。
3. 企画のコンセプト
企画のコンセプトでは企画の目的や狙いを明確に示し、プロジェクトの内容を詳細に説明します。企画の独自性や革新性など、他社との差別化ポイントを強調すると良いでしょう。
ターゲットとする顧客層や市場を具体的に設定し、企画が実現するとどのような価値を提供できるかをアピールできると説得力が増します。また、コンセプトを端的に表現するキャッチフレーズを用いるのも効果的です。
4. 企画を実施するメリット・デメリット
次に、企画を実施することで得られるメリットを明確に提示します。売上拡大やコスト削減・顧客満足度向上など具体的なメリットを数値化して示します。
また、企画を実施することで生じる可能性があるデメリットも忌憚なく記載することも大切です。初期投資の増加やリソースの不足・既存事業への影響など考えられるデメリットを洗い出しましょう。デメリットへの対策や軽減策もあわせて提示することで、企画の実現可能性を効果的にアピールできます。
メリットとデメリットを比較考量し企画の妥当性を評価する材料を提供できれば、ものごとを客観的に捉えて企画を立案している姿勢を効果的に伝えられるでしょう。
5. 運営体制
運営体制の項目は、プロジェクトチームの構成メンバーやその役割分担などを記載します。外部パートナーやベンダーとの協力体制についても明記していると、組織がどのように動くのかについてより詳細に伝えられます。
また、ヒト・モノ・カネのリソースがどの程度必要かについて数値で具体的に記載されていると、実現可能な企画かどうか判断しやすくなるでしょう。
6. スケジュール
スケジュールは、企画の実現可能性を評価する重要な判断材料です。プロジェクトを実行するにあたって、どのくらいの期間をかけて誰が何を実行するのかを具体的に明記しましょう。
主要なマイルストーンとなる節目を設定し、それぞれの達成目標が書かれているとプロジェクトの進め方がイメージしやすくなります。このとき、あまりにもタイトなスケジュールを設定しないようにしましょう。余裕がないスケジュールを提示してしまうと、実現できない可能性が高いと判断されかねません。
社内外の環境要因やトラブルなどのスケジュールに影響を与える不確定要素を考慮して、余裕を持ったスケジュールを組むのがポイントです。
7. 会社概要・問い合わせ先
企画書の最後に、会社名・所在地・代表者名などの会社情報を記載しておきましょう。また社外に見せる企画書の場合は、問い合わせ先として担当者の氏名や連絡先(電話番号・メールアドレス)を明記します。
弊社ストリームラインでは資料制作のご依頼を承っています。ホワイトペーパーの作成についてお困りの方は資料作成のワンストップ代行サービス「バーチャルプランナー」までお気軽にご相談ください。
企画書を書くときに役立つフレームワーク
企画書を作成する際に役立つフレームワークを4つ紹介します。
- 6W2H
- CTPT
- 3C分析
- SWOT分析
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 6W2H
6W2Hとは企画の具体的な内容を整理するためのフレームワークです。企画書をまとめる際に重要な着眼点として、英語における疑問詞の頭文字を取り「6W2H」にまとめています。
| 項目 | 内容 |
| なぜ (Why) | この企画を実施する必要があるのか |
| 何を (What) | どんなサービス内容なのか、どんな内容の企画なのか |
| どこで (Where) | どこの市場に参入するのか、どこで実施するのか |
| いつ (When) | いつ実施するのか |
| 誰が (Who) | 誰がこの企画を実行するのか |
| 誰に対して (Whom) | ターゲットは誰なのか |
| どうやって (How to) | どんな方法で実施するのか |
| いくらで (How much) | いくらの資金が必要なのか |
各項目について具体的に検討していくことで、抜け漏れやダブりのない企画書が作成できるでしょう。
2. CTPT
サービスの内容が優れていても企画書の内容に説得力がないと、企画が採用されないこともあります。そこで、企画の内容に厚みを出すためのフレームワークが「CTPT」です。
6W2Hはビジネスシーンで汎用的に使用できるフレームワークであるのに対して、CTPTはマーケティングのフレームワークであるため、商品やサービスの企画書を作成する際に有効です。
各要素の概要は以下のとおり。
| 項目 | 概要 |
| C (コンセプト) | 商品やサービスの特性。ターゲットに提供する価値を明確にする。 |
| T (ターゲット) | 顧客。商品やサービスを受け取る対象となる人々。 |
| P (プロセス) | ターゲットにコンセプトを理解してもらうまでの過程。 |
| T (ツール) | コンセプトを伝えるための方法。実現のための手段。 |
まずは、C(コンセプト)とT(ターゲット)を設定します。
コンセプトとは商品やサービス、ターゲットは顧客を指します。つまり「どのような特性を持った商品・サービスを、誰に向けて提供していくか」を決める工程です。
コンセプトとターゲットの整合性が取れていることが重要で、この2つがマッチしていないと良い企画とは言えません。コンセプトがどれほど良かったとしても、明確なターゲットやニーズが存在しなければ、実現は難しいでしょう。
次に、実現方法を検討するためにP(プロセス)とT(ツール)を設定します。プロセスは設定したターゲットにコンセプトを理解してもらうまでの過程、ツールはコンセプトを伝える方法にあたります。
「どのような段取りで、どのような手段で提供していくか」を決め、企画を実現するためのアクションプランを立てていきましょう。
コンセプトとターゲットの整合をとり、企画を実現するためのアクションプランとしてプロセスとツールを設定すると、説得力のある資料を作成できます。
3. 3C分析
3C分析は、企画書作成の際に、市場環境を整理するためのフレームワークです。3つのCとは、Customer(顧客)・Competitor(競合)・Company(自社)を指し、各項目の概要は以下のとおりです。
| 分析項目 | 内容 |
| Customer (顧客) | ターゲット顧客のニーズ・行動特性・購買プロセスなどを把握する。 |
| Competitor (競合) | 競合他社の強みや弱み・戦略などを分析し、自社との差別化ポイントを明確にする。 |
| Company (自社) | 自社の強みや弱み・リソースなどを整理し、企画の実現可能性を評価する。 |
たとえば、IT・ソフトウェア開発会社が転職サポートサービスを開発する際の企画書を作成する場合、3C分析は以下のように活用できます。
| 分析 | 内容 |
| Customer (顧客) | ターゲット:IT業界で働く20代〜30代のエンジニアニーズ:スキルアップのための情報、企業の技術スタックなど企画書に反映するポイント:ニーズに合わせた情報提供やサービス設計 |
| Competitor (競合) | 競合:既存の転職サイトやエージェント差別化ポイント:AIを活用した求人マッチング、業界出身のキャリアアドバイザーによる手厚いサポート企画書に反映するポイント:競合との差別化ポイント |
| Company (自社) | 強み:技術力やリソースを活かした内製開発が可能弱み:初期開発コスト、専門人材の確保企画書に反映するポイント:強みを活かした企画、課題に対する対策を示すことで実現可能性を高める |
このように3C分析の結果を企画書の各パートに具体的に落とし込めば、説得力のある内容になるはずです。市場環境や自社の強み・課題を明確に示すことが、企画書作成において非常に重要なポイントと言えます。
4. SWOT分析
SWOT分析は、自社の内部環境と外部環境を分析するためのフレームワークです。SWOTとは、Strengths(強み)・Weaknesses(弱み)・Opportunities(機会)・Threats(脅威)の頭文字を取ったもので、各項目の概要は以下のとおりです。
| 項目 | 概要 |
| Strengths (強み) | 自社の内部環境における強み。企画実現に役立つ要素。 |
| Weaknesses (弱み) | 自社の内部環境における弱み。企画実現における課題やリスク。 |
| Opportunities (機会) | 市場における機会。企画の成功要因となる外部環境。 |
| Threats (脅威) | 市場における脅威。企画の障壁となる外部環境。 |
たとえば、IT業界における転職支援サービスに関する企画書を作成する場合、SWOT分析は以下のように活用できます。
| 項目 | 内容 | 企画書への反映例 |
| Strengths (強み) | 高度な技術力IT業界に精通した人材豊富な開発実績 | AIを用いた求人マッチングシステム開発業界知識に基づいた的確なキャリアアドバイス提供 |
| Weaknesses (弱み) | 転職サービス運営ノウハウ不足ブランド認知度が低い | 外部パートナーとの提携積極的なマーケティング施策の実施 |
| Opportunities (機会) | IT業界の転職需要の高まりDXの進展に伴うエンジニア不足 | 市場ニーズに対応したサービス提供社会貢献性の高いサービスとしてアピール |
| Threats (脅威) | 競合他社の動向景気悪化による転職市場の冷え込み | サービスの差別化コスト管理の徹底 |
SWOT分析の結果を企画書の現状分析やリスク対策のパートに盛り込めば、説得力のある企画書を作成できます。
企画書を書く際のポイント
次に、企画書を書く際に意識すべき点について紹介します。
- フレームワークを活用して抜け漏れをなくす
- いきなりスライド作成に着手しない
- 伝わりやすいデザインを心がける
- 数値目標を提示する
企画書の作成を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. フレームワークを活用して抜け漏れをなくす
企画書は「なんとなくアイデアを思いついた」段階で作り始めてしまうと、必要な情報の抜け漏れが生じます。
企画を書面に落とし込んでいくためには「企画書を書くときに役立つフレームワーク」で解説したフレームワークが有効です。情報を整理するための枠組みを活用すれば、読み手に疑問点を残さない網羅的な企画書を作成できます。
2. いきなりスライド作成に着手しない
企画書を作成するにあたって、いきなりスライド作成に着手するのは避けましょう。まずは、企画書の構成を十分に検討することが重要です。スライド作成から始めてしまうと、いつの間にか論理が破綻してしまったり情報の抜け漏れが発覚したりして、修正に多くの時間がかかってしまう恐れがあります。
まずは紙やWordファイルなどに、内容を箇条書きで書き出してみましょう。その状態で内容の抜け漏れをチェックし、盛り込む順番などを決めてからスライド作成に着手するようにしてください。
3. 伝わりやすいデザインを心がける
図など視覚で伝える要素の大きいパワーポイントで企画書を作成する場合、伝わりやすいデザインであることは非常に重要です。人間の第一印象は「視覚」による影響が5割以上とも言われています。
読みやすいフォント、色の選び方、レイアウトのルールなど、パワーポイントで企画書を作る際に最適なデザインになるように心がけてください。
パワーポイントのデザインについては下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
4. 数値目標を提示する
プロジェクトの目的を達成するための具体的な数値目標を設定し、企画書に明記することも大切なポイントです。売上高や利益率・顧客数など、企画の成果を評価する指標を選定します。
現状の数値と目標値を比較し、達成すべき改善幅を明確にしましょう。目標値は高すぎず低すぎない、現実的かつチャレンジングな水準に設定します。数値目標を提示することで、企画の実現可能性や妥当性を客観的に示せます。
目標達成のための施策や活動計画も合わせて提示すれば、実現性を効果的にアピールできるでしょう。
企画書を書く際に参考になるテンプレート
ここでは、企画書を作成する際のテンプレートを紹介します。企画書作成に必要な項目をピックアップしてあるため、事前にテンプレートに沿ってアイデアや情報を整理しておけば、資料の作成がスムーズになるでしょう。
1. 表紙
- 企画書
- タイトル
- 提案者名
- 提出日
2. 現状分析・企画背景
- 現状の問題点
- 市場動向
- 企画の必要性
3. 企画コンセプト
- 目的・狙い
- 独自性・差別化ポイント
- ターゲット顧客・市場提供価値
- 具体的な商品・サービス内容
- 特徴・強み
- 実現方法
4. メリット・デメリット
- 期待される効果(数値化)
- 考えられるリスク・課題
- 対策・軽減策
5. 運営体制
- 実行体制(人員・役割)
- 意思決定プロセス
- 外部協力者
6. スケジュール
- 開始日・終了日
- マイルストーン
- タスク・担当者
8. 会社概要・問い合わせ先
- 会社情報
- 事業内容
- 担当者連絡先
あらかじめこのテンプレートの項目に沿って情報を取捨選択すれば、PowerPointやWordで企画書を作成する際の土台ができあがります。図表なども活用しながら項目ごとにポイントをまとめて、説得力のある企画書を目指しましょう。
企画書の書き方における具体例
では実際に、企画書のテンプレートに沿って作成した企画書の下書きを紹介します。
「IT・ソフトウェア開発の会社において、転職サポートサービスの開発案件の企画書を作成する」という場合を仮定すると、以下のようにテンプレートを活用できます。
1. 表紙
- タイトル:IT業界特化型転職サポートサービス「〇〇」の開発
- 提案者名:〇〇〇〇
- 提出先:株式会社〇〇 経営企画部
- 提出日:2023年6月1日
2. 現状分析・企画背景
- IT業界の転職市場は活況だが、専門性の高いマッチングサービスが不足
- エンジニアの転職ニーズが高まっており、適切な求人情報提供が必要
- 自社の技術力を活かした新サービス開発で、事業領域拡大を図る
3. 企画コンセプト
- IT業界に特化した転職サポートサービスを開発し、エンジニアの効果的な転職を支援
- AIを活用した求人マッチング機能と、業界専門のキャリアアドバイザーによる手厚いサポートが強み
- ターゲットは、IT業界で働く20代〜30代のエンジニア
- ユーザーに最適な求人情報を提供し、スムーズな転職を実現
- Webサイト・アプリを通じて、ユーザーの経歴・スキルに合わせた求人情報を提供
- AIアルゴリズムを用いて、ユーザーと求人のマッチング精度を向上
- IT業界出身のキャリアアドバイザーが、カウンセリングや面接対策など転職支援を提供
- 自社のエンジニアリソースを活用し、内製開発を行う
4. メリット・デメリット
- 新規事業として、収益拡大が見込める(会員数1万人、売上高2億円を目標)
- 自社サービスとの相乗効果で、ブランド力向上にもつながる
- 初期開発コストや専門人材の採用などに時間とコストがかかる可能性あり
- サービス認知度向上のための、マーケティング施策が必要
5. 運営体制
- 社内にプロジェクトチームを結成(企画・開発・マーケティングなど各部署から人員を選抜)
- プロジェクトリーダーを中心に、定期的な進捗会議を実施
- 外部のデザイン会社や人材紹介会社と連携し、サービス品質を担保
6. スケジュール
- 開始日:2023年7月1日
- サービスリリース目標:2024年10月1日
- マイルストーン:要件定義(8月)/設計・開発(9月〜翌5月)/テスト・改修(6月~9月)
- 主要タスクと担当者:要件定義(企画部門)/UIデザイン(デザイン会社)/開発(開発部門)など
7. 会社概要・問い合わせ先
- 株式会社〇〇
- 事業内容:ソフトウェア開発、Webサービス運営
- 担当者:〇〇〇〇(〇〇〇〇@example.com / ××-××××××××)
企画書を作成する際に工夫すべきポイントは、以下のとおりです。
- 明確な企画背景と目的を提示し、事業の必要性を強調する
- ターゲットユーザーと提供価値を具体的に設定し、焦点を絞る
- サービスの特徴と差別化要因を明示し、競合との違いを際立たせる
- 数値目標を設定し、事業のポテンシャルを明確に示す
- リスクと対策を検討し、実現可能性を高める
- 運営体制とスケジュールを明示し、プロジェクトの実行力を証明する
このようなポイントを意識すれば、説得力のある企画書を作成できるでしょう。
書き方を押さえてわかりやすい企画書を作成しよう!
企画書は、新しいアイデアを実現するための第一歩です。本記事で紹介した企画書を作成するうえでのポイントを意識しつつテンプレートを活用すれば、説得力のある企画書に仕上げられるでしょう。
ぜひ本記事で紹介したポイントを参考に、説得力のある企画書を作成してみてください。