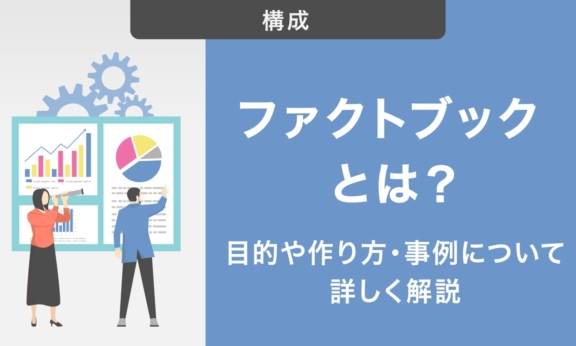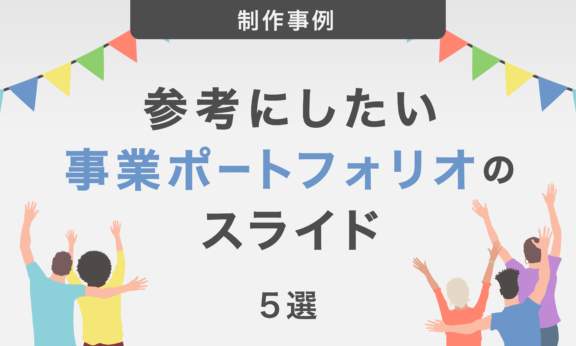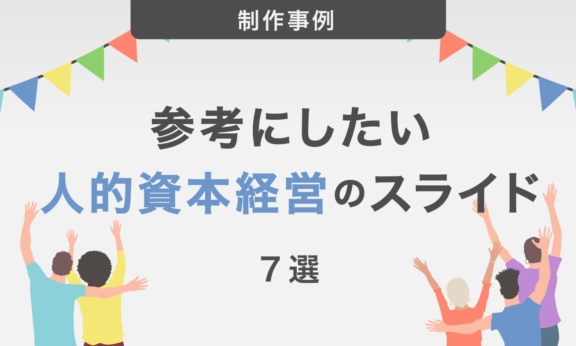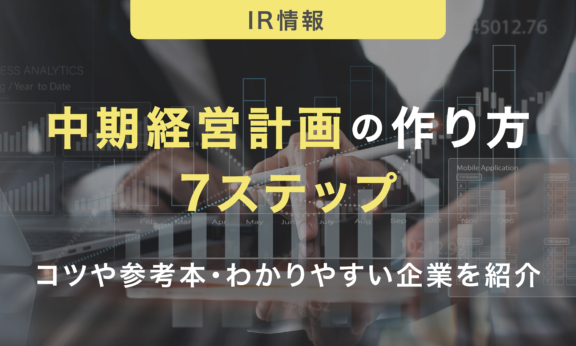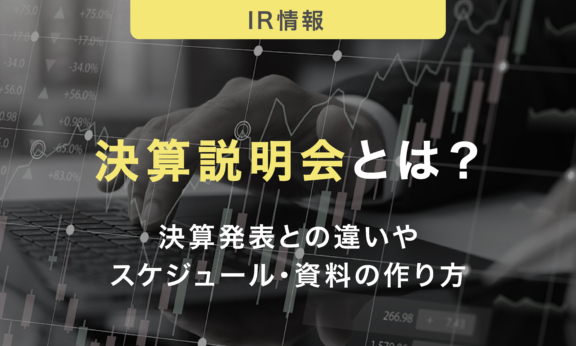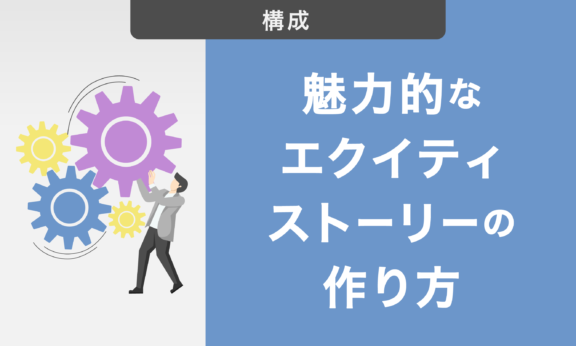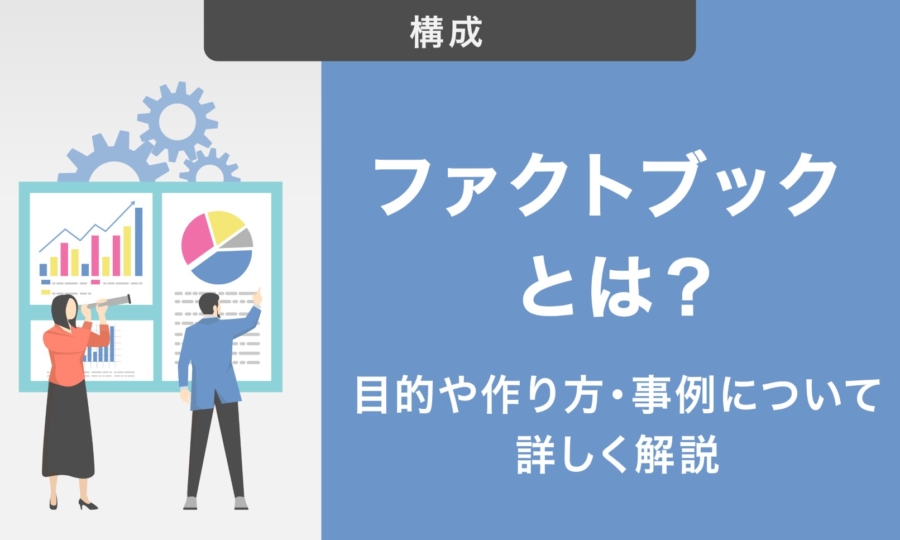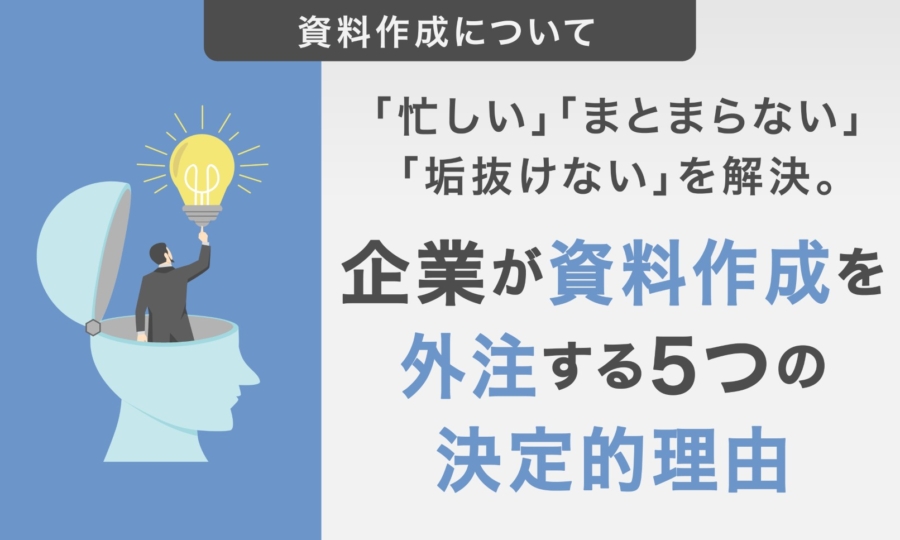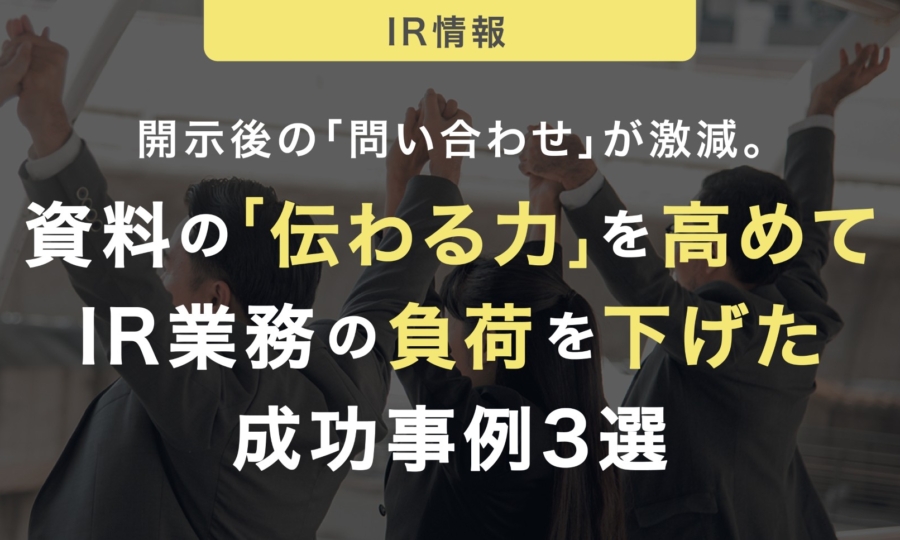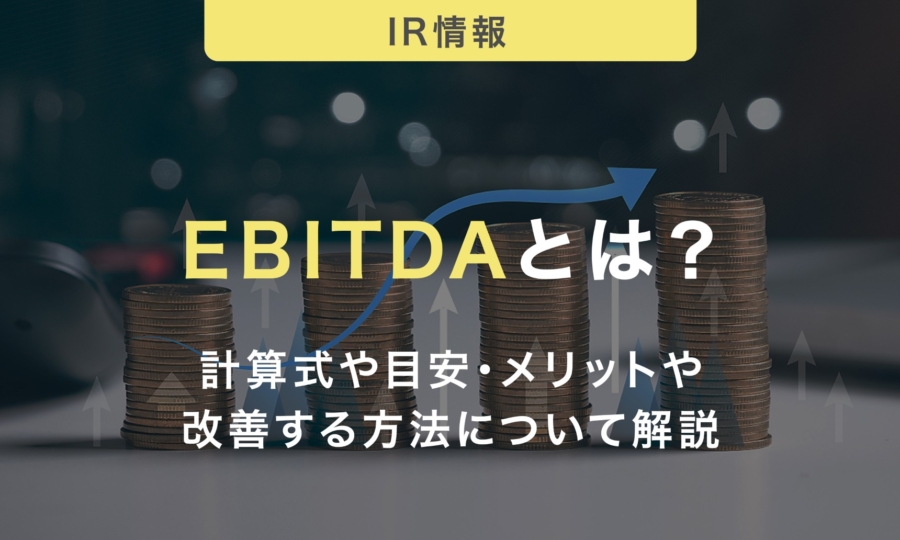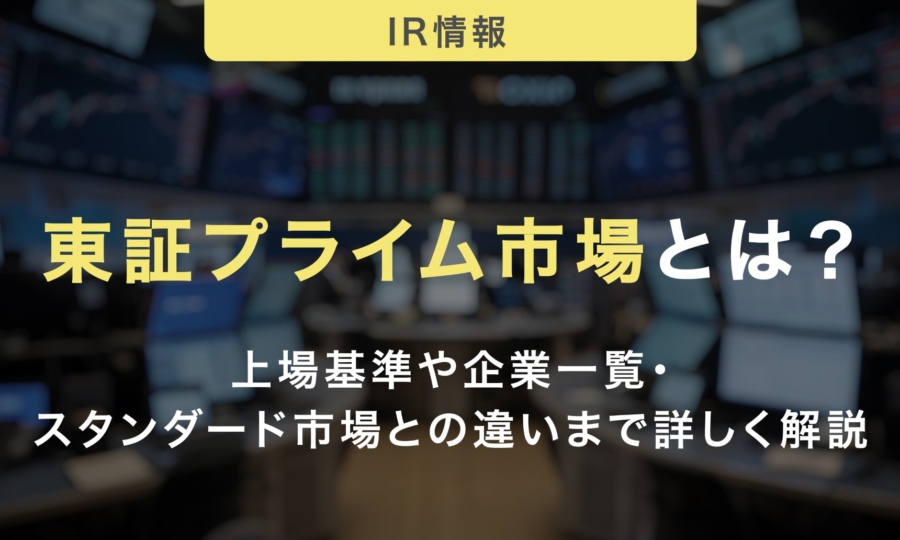営業資料でやってはいけない8つのNGと改善ポイントを徹底解説
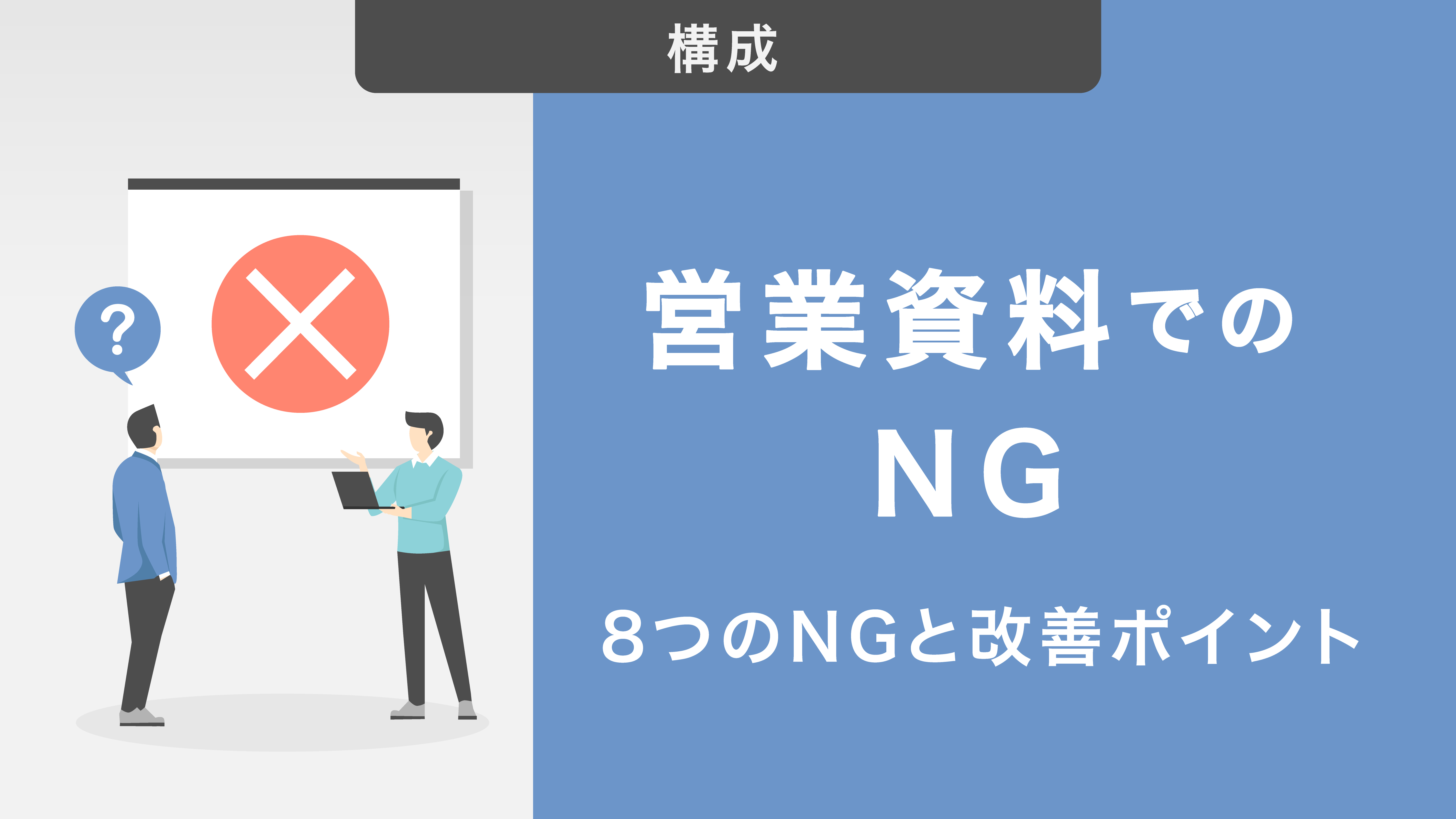
本記事では、営業資料でやってはいけない8つのNGとその解決策を徹底解説します。
具体的には、理解しづらい表現や資料の曖昧さを改善し、説得力を高めるための対処法を紹介します。
この記事から読み手に響く資料作りのポイントを学び、効果的な営業活動を実現していきましょう。
細部までこだわった資料作成には、膨大な時間と専門スキルが必要…
バーチャルプランナーなら、企画構成からデザインまで完全オーダーメイド。
貴社の負担をゼロにし、理想の資料を形にします。
目次
・1. 専門用語や社内用語の使用を避ける・2. 競合優位性と具体的メリットを明確化する・3. 客観的事実に基づく信頼性の高い根拠(エビデンス)を示す・4. 顧客の理解を妨げない論理的な構成(ストーリー)を組む・5. 迷いを与えない明確なCTA(行動喚起)を設置する・6. 全体を通した一貫性のあるストーリー構成を意識する・適切な情報量を確保し、読み手の満足度を高める・8. 顧客ニーズを優先し、求める情報を網羅する
1. 専門用語や社内用語の使用を避ける
社内独特の表現や業界内での専門用語は、そのコミュニティーに所属していない方からすると、非常に理解しづらい言葉です。
営業資料の読み手となる顧客がその分野に精通している場合は問題ないかもしれません。
しかし、そうでなかった場合、読み手の理解を阻害するだけでなく、「相手に配慮ができない人」と捉えられてしまうため注意が必要です。
NG1への対処法:顧客視点に立った分かりやすい表現への変換
重要なことは、読み手に「読んでもらい」、「理解してもらう」ことです。
単純なことかもしれませんが、相手が理解できるやさしい言葉で表現することが最も大切です。
2. 競合優位性と具体的メリットを明確化する
自社の強みや他社との差別化が曖昧な表現では、顧客にその価値を十分に伝えることができません。
多数のサービスが乱立し、多くの企業が類似サービスを提供する昨今、他社より優れている点を明確に示さないと、顧客はそのサービスを選ぶ理由が見えにくくなります。
NG2への対処法:定量データを用いた独自の価値(USP)の提示
具体的な事例や独自のアプローチを含めることで、自社の強みを明確にする必要があります。
たとえば「当社は、全国に在宅のエンジニアチームを配置しているため、24時間365日、どの時間帯でも1時間以内に対応が可能です。」のように、具体的な数字や他社との比較を盛り込むと顧客にとってのメリットが一目でわかるようになります。
このように、サービスの特徴を曖昧にせず、「具体的なメリット」「実現できる理由」「他社との差異」をしっかりと示すことが、顧客に対する説得力を高めるポイントです。
3. 客観的事実に基づく信頼性の高い根拠(エビデンス)を示す
曖昧な主張や根拠のない説明は、読み手に不安を与え、信頼を失う原因になります。
たとえば「事務作業はシステムで代替できるものがほとんどです」という表現では、具体的な裏付けがなく、読み手に疑念を抱かれてしまいます。
NG3への対処法:数値実績や導入事例による説得
信頼を高めるためには、具体的なデータや事実に基づく説明が必要です。
たとえば、「受注作業から請求書発行までのプロセスをシステムで代替した結果、社員1人あたり月に50時間の作業時間が削減されました。」というように、具体的な数値や実績を示すことで、説明に信頼性が加わります。
4. 顧客の理解を妨げない論理的な構成(ストーリー)を組む
説明の順番がバラバラだと、読み手は混乱し、内容が頭に入ってきません。
たとえば、口頭説明では「導入のメリット」を最初に伝えているのに、資料では「サービスの概要」が先に来ていると、読み手はどこに注目すべきか迷ってしまいます。
NG4への対処法:読み手の疑問に順次応える情報設計
理想的な資料作りは、紙芝居の読み聞かせのように、話し手と読み手が同じタイミングで同じ内容に集中できるようにすることです。
つまり、顧客が最初に知りたい情報が何かを考え、説明の流れをそれに合わせて構成する必要があります。
5. 迷いを与えない明確なCTA(行動喚起)を設置する
資料を通じて顧客の興味を引くことに成功しても、次のアクションを促す情報が含まれていないと、ビジネスチャンスを逃してしまうことがあります。これは非常にもったいないことです。
NG5への対処法:問い合わせ先や次のステップを具体的に明記する
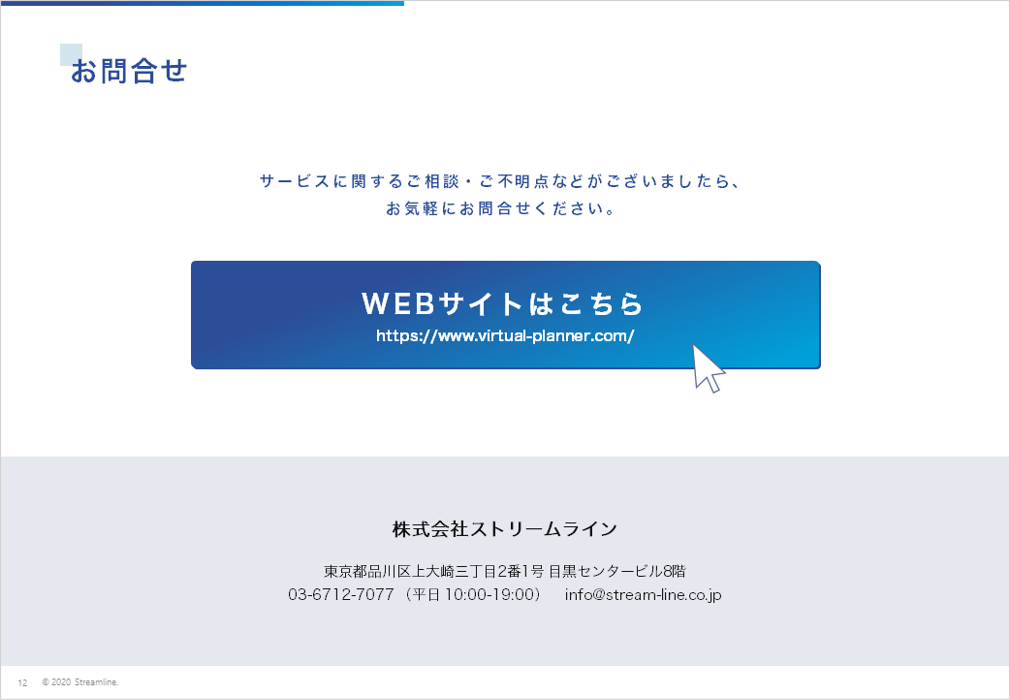
資料には「CTA」、つまり電話番号、メールアドレス、担当者や部署の連絡先などを明記しておくことが重要です。
例えば、最後のページに「今すぐお問い合わせください」、「詳細な資料をご請求ください」といった次のアクションを促す情報が記載されていれば、顧客は自然と次のステップに進みやすくなります。
このように資料作成の際は、ただ情報を伝えるだけでなく、顧客に行動を促す「次の一手」をしっかりと示すことを忘れないようにしましょう。
6. 全体を通した一貫性のあるストーリー構成を意識する
資料を作成していると、つい情報を詰め込みすぎてしまうことがあります。
資料作成の経験が豊富な人は自然と情報を整理して、一貫性ある資料を作ることができますが、慣れていない方が作成した場合は情報が錯綜することがあります。
その結果、資料全体を通して伝えるべき内容が定まらず、読み手は全体を通して「何が重要であるか」わからなくなり、混乱してしまうことがあります。
NG6への対処法:基本的な構成案(課題・解決・証拠・提案)の活用
資料の流れは、対象となる相手や目的に応じて変わります。そのため、必ずしもすべての資料が同じ構成になるわけではありません。
しかし、基本的な構成を理解することは重要です。なぜなら、その構成を参考に自分なりのアレンジをすることが可能になるためです。
基本的な構成の例としては、下記に記載する内容がよく挙げられます。資料作成に慣れていない方は、手始めにこの基本的な構成から参考にしてみてください。

- 課題: お客様の悩みや不安を明確にする
- 解決策: その問題を解決する方法を示す
- 証拠: 解決できる具体的な根拠やデータを提示する
- 提案: 相手にとって魅力的な提案を行う
- 安心材料: 相手の不安を和らげる情報を提供する
- 行動喚起: 具体的な次のステップを促す手段を示す
資料の構成からデザインまで、ワンストップで外注したい方へ
日々のコア業務で忙しい中、資料の構成をイチから考え、それをデザインに落とし込んでいくのは非常に手間も時間もかかる作業です。
累計支援数1,000社超の実績を持つVIRTUAL PLANNERなら、まとまりきっていない情報を渡すだけでOK。専任のコンサルタントが要点を整理し、最適な構成案を作成。パワーポイント専門のデザイナーが細部までこだわったスライドをオーダーメイドでデザインします。
適切な情報量を確保し、読み手の満足度を高める
スライドの枚数は必ずしも多ければ良いというわけではありません。
しかし、あまりに枚数が少なすぎると読み手に情報不足な資料だと感じられる恐れがあります。
状況や相手が求める情報を考慮せずに、資料の枚数が少なくなることは避けたいところです。
NG7への対処法:最低10枚を基準とした充実したスライド構成
資料作成に慣れておらず、適切な枚数や文量がつかめていない方は、10枚以上のスライドを入れることを基準にしましょう。
この点を認識した上で重要なことは、適切な情報量を盛り込み、読み手を満足させることです。
8. 顧客ニーズを優先し、求める情報を網羅する
資料を作成する際、読み手が求めている情報がきちんと含まれていないと、営業で達成したい目的が達成できないことがあります。
この事態に陥らないためにも下記で紹介する項目を記載して、読み手が次にどんなアクションを取りたいかを考慮し、必要な情報を盛り込むことが重要です。
NG8への対処法:Webリンクや参考資料による情報の補完
読み手が知りたい情報を掲載した資料を作るには、読み手が次にどのような行動を取りたいかを意識することが重要です。
その上で、詳しい情報が必要だと判断できた場合は、詳細を把握できるWebサイトへアクセスできるリンクを設置したり、あらかじめ必要な情報を別の参考資料に記載するのが良いでしょう。