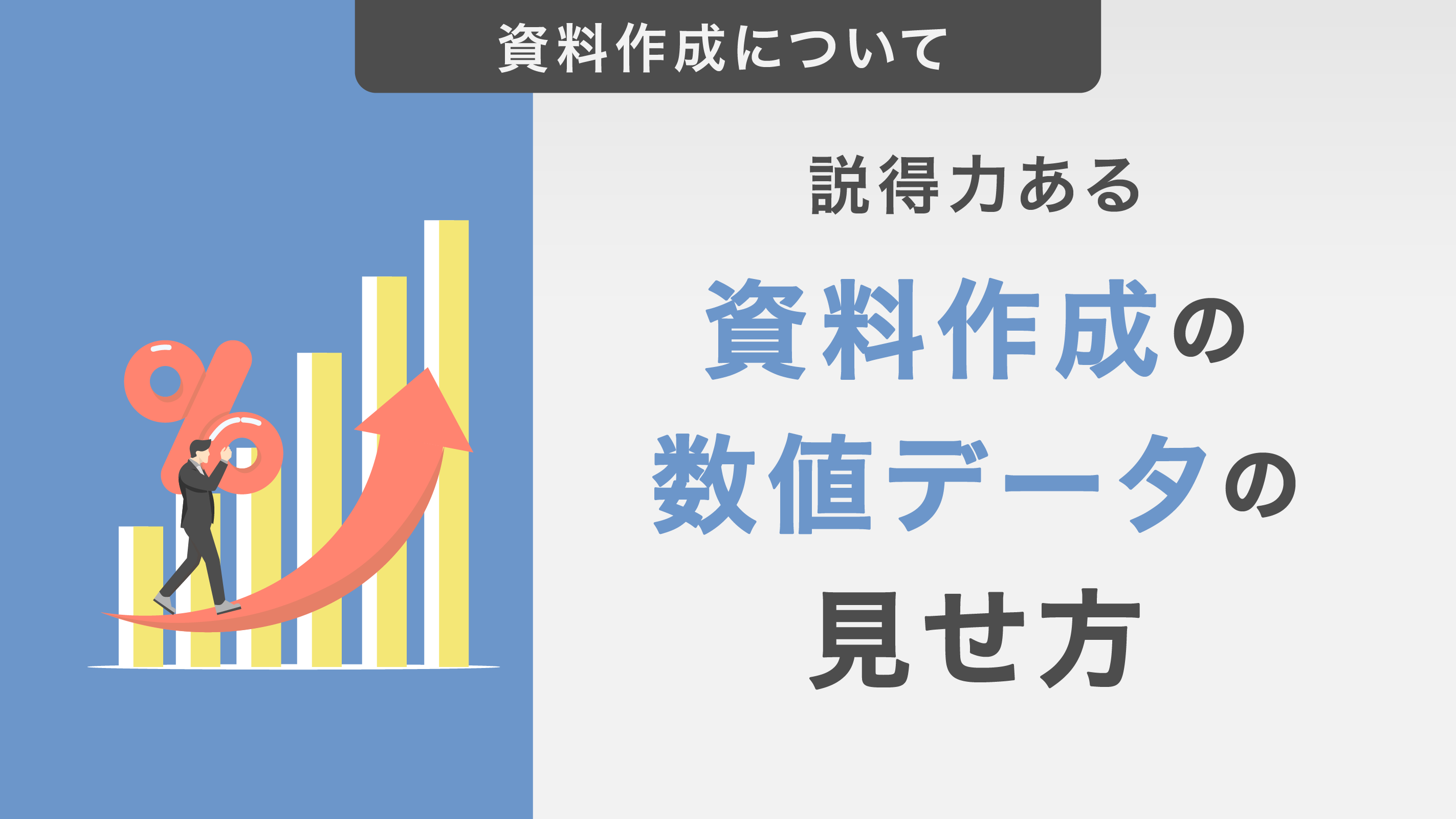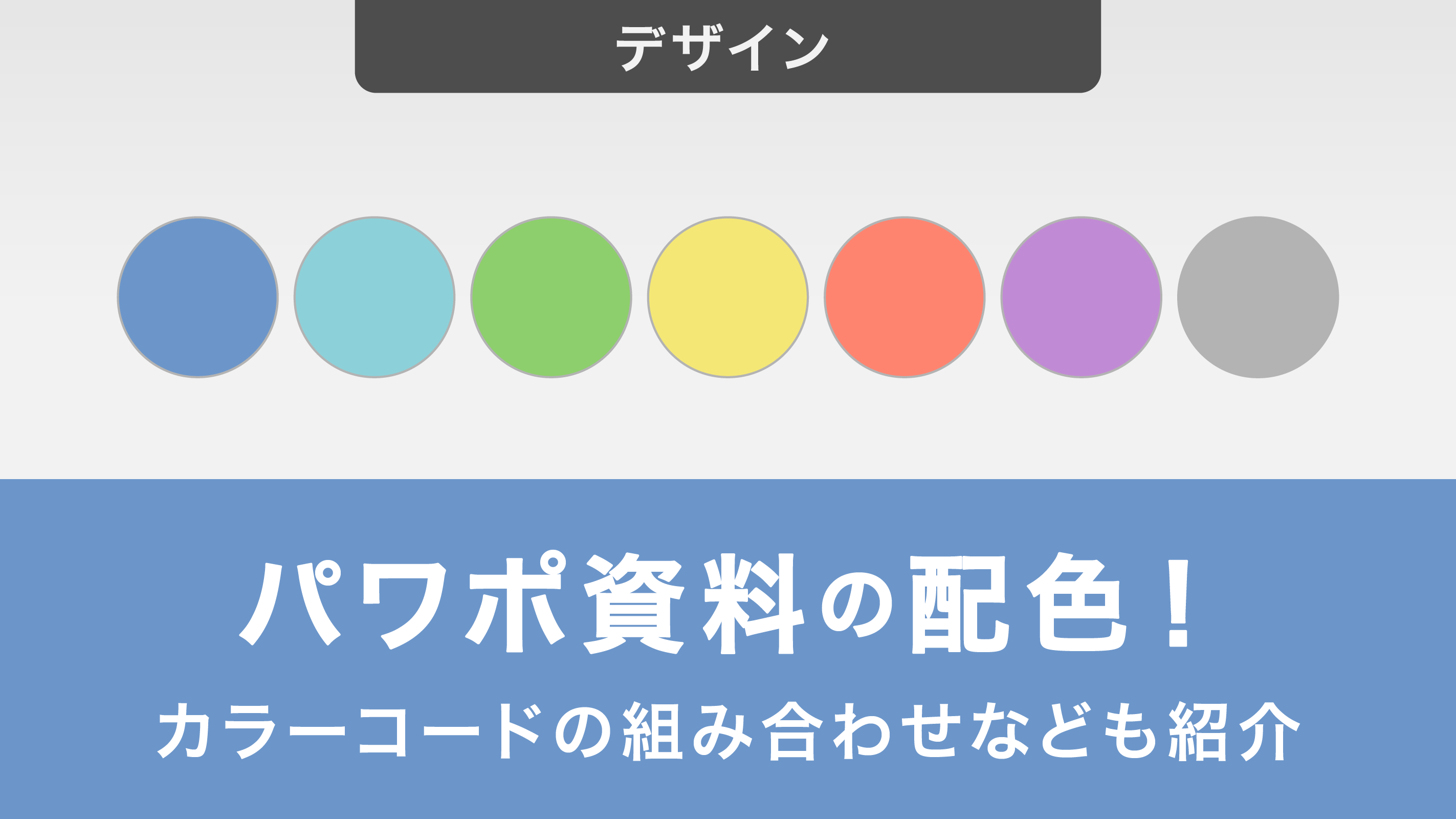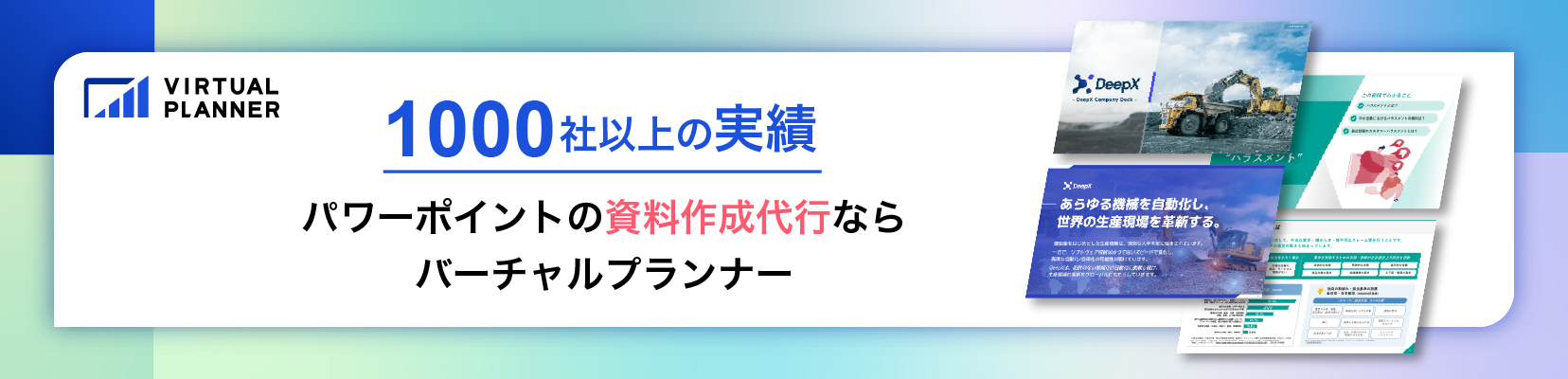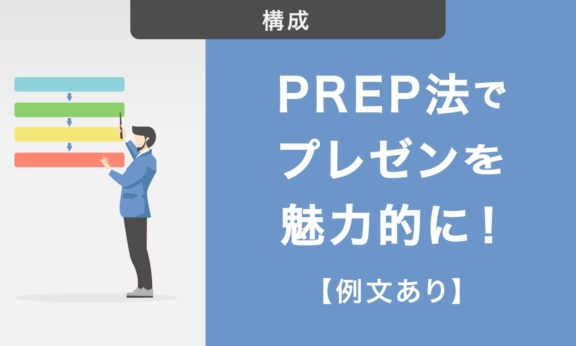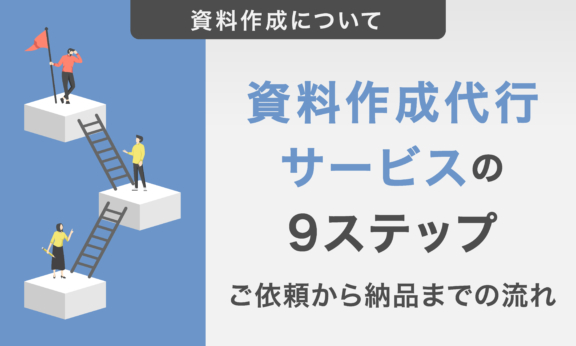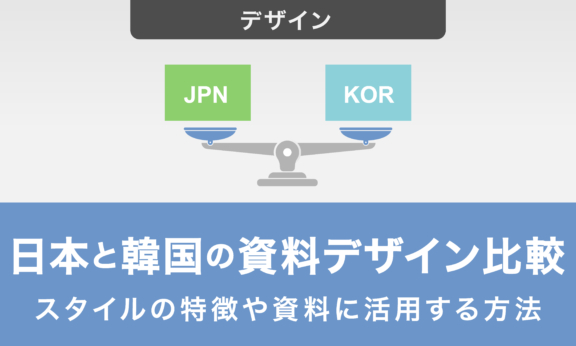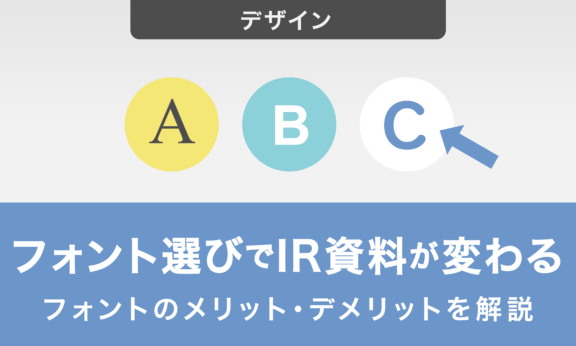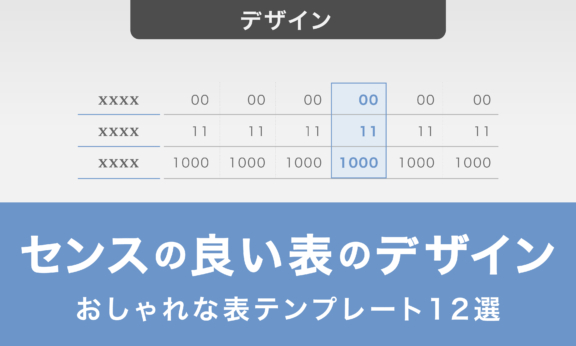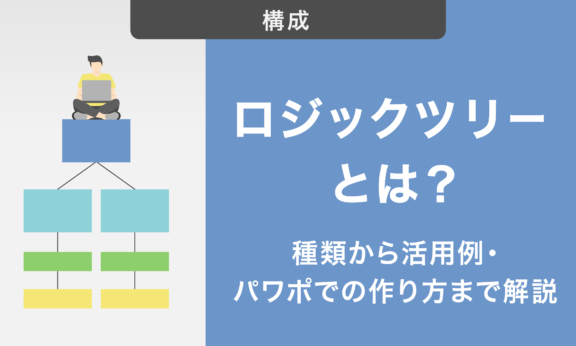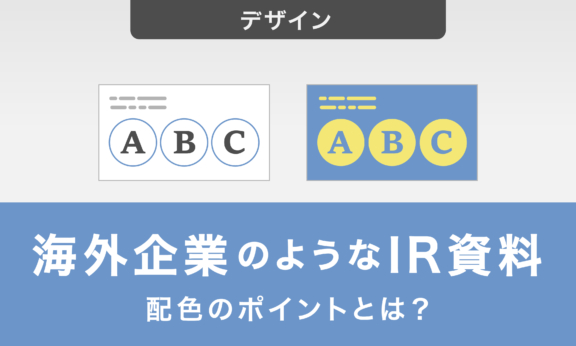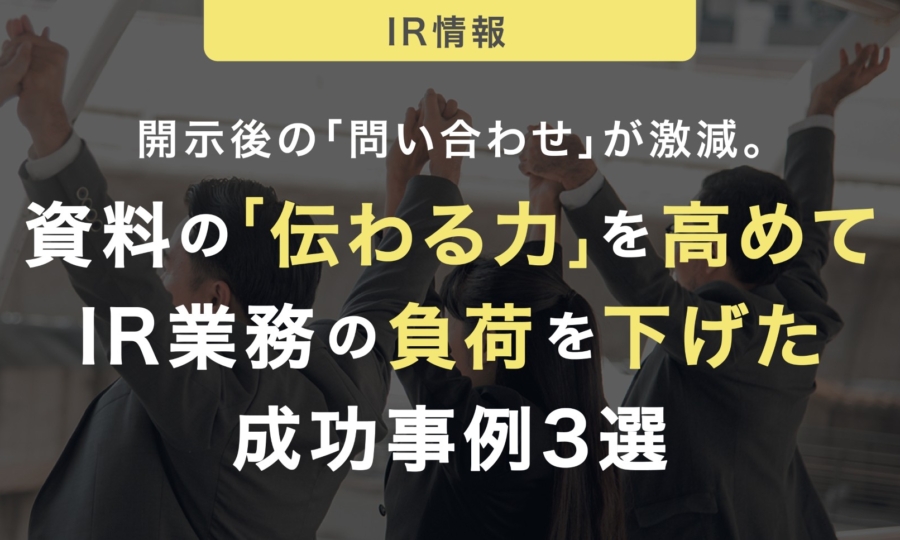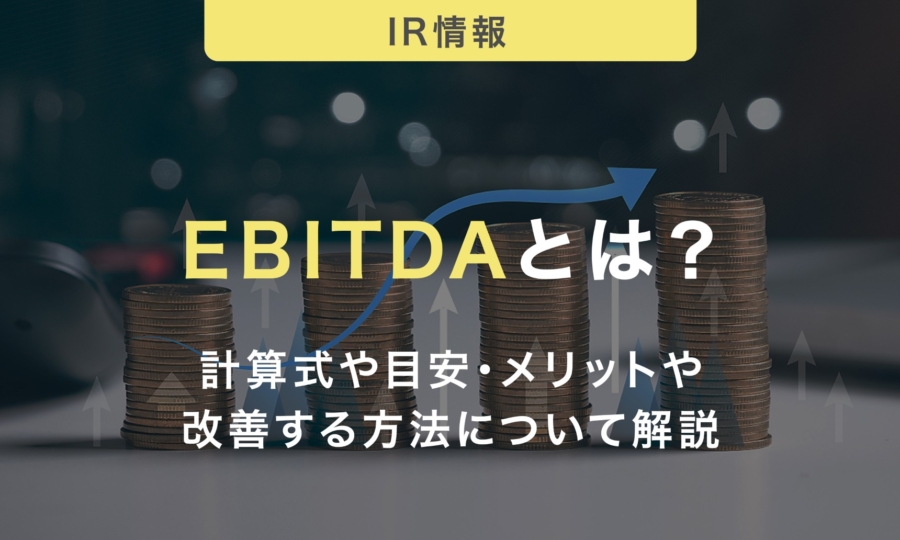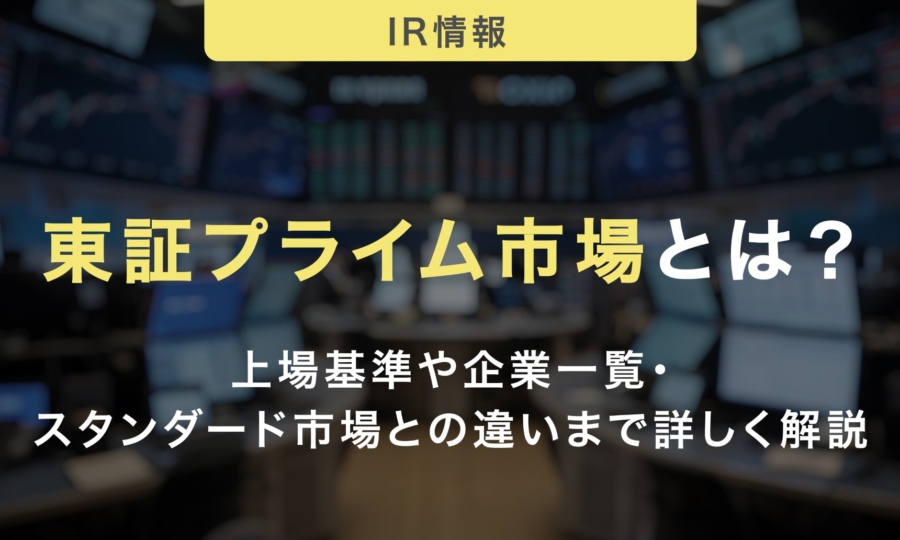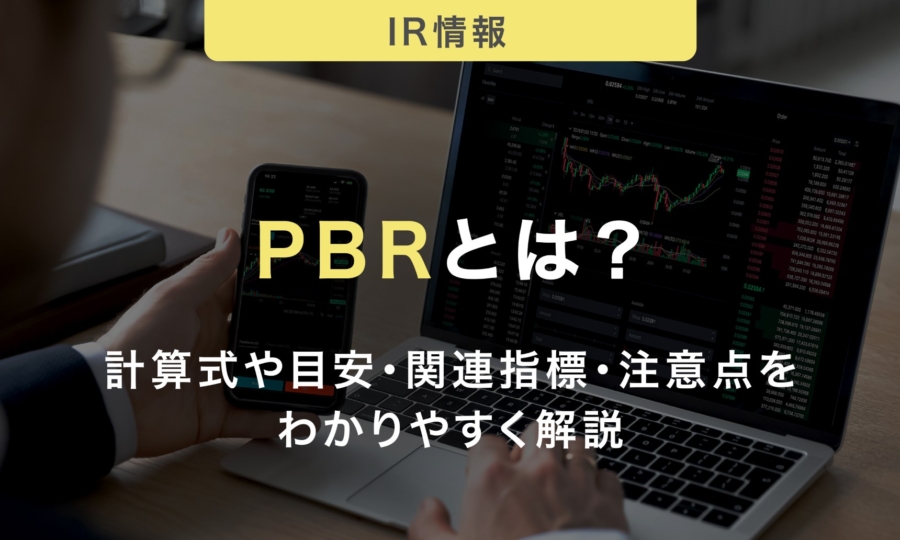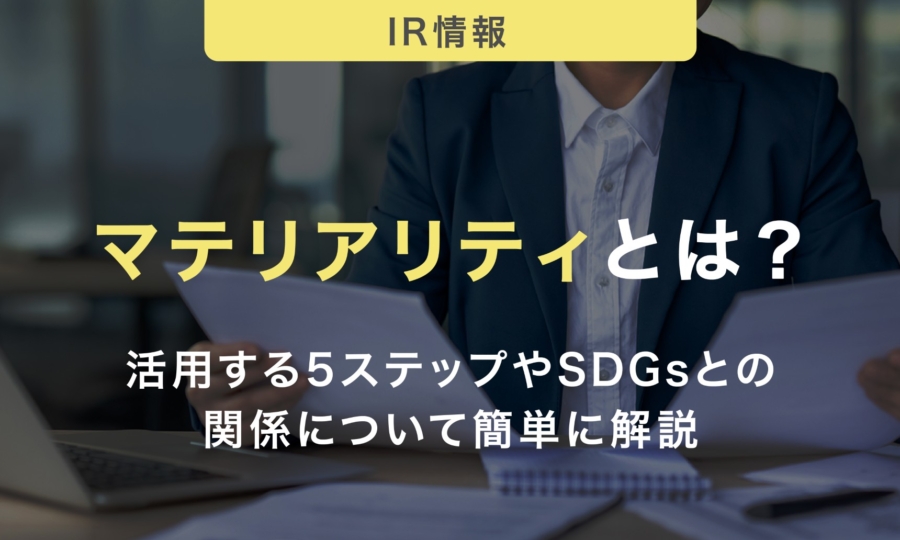パワーポイントの構成例5選!資料を作る際の構成要素やコツについても紹介

パワーポイントで資料を作成する際、最も重要なのは構成です。しかし、多くのビジネスパーソンは資料の構成に悩み、作成に必要以上の時間を費やしています。
そこで本記事では、すぐに実践できる基本的な構成パターンを5つ紹介します。また、資料作成の効率を上げる具体的なコツや、目的別の構成要素についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
本記事の内容を参考にすれば、短時間で説得力のある資料を作成できるでしょう。
なお、弊社ストリームラインには1,000社を超える資料制作の実績があります。「自社で資料制作する人的リソースを割けない」「クオリティが高い資料を用意したい!」という方は、弊社の資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」にぜひご相談ください!
目次
・パワーポイントでプレゼン資料を作る際の構成要素・パワーポイントでプレゼン資料を作成する際の構成例5選・パワーポイントで見やすい構成を組み立てるコツ・パワーポイントの構成を整えればわかりやすい資料を作成できる
パワーポイントでプレゼン資料を作る際の構成要素
わかりやすいプレゼン資料を作るには、基本となる構成要素を意識することが大切です。プレゼン資料を作成する際の基本的な構成要素について、以下の4つを詳しく解説します。
- 大結論
- キーメッセージ
- サブメッセージ
- ファクト
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 大結論
大結論は、資料のテーマ全体のことを指します。プレゼンテーションの目的を明確に示し、聴衆に最も伝えたい核心的なメッセージを簡潔に表現したものです。
序論や本論で展開した内容の要点を集約し、プレゼンテーション全体を通じて一貫性のある主張を示す役割があります。
最終的な結論部分では、導入部で提示した問いに対する答えや、印象的な引用を用いることで、より強い印象を残せます。
2. キーメッセージ
キーメッセージは、各スライドで最も伝えたい内容を簡潔に表現したものです。タイトルの下に配置し、そのスライドの結論や要点を明確に示す役割があります。
キーメッセージを作る際は、新聞記事における冒頭の要約文のように、読み手が短時間で内容を把握できることを意識しましょう。
たとえば、平仮名や助詞を極力省き、数字はわかりやすく概数で表現するなど、直感的に理解できるよう工夫することが重要です。
とくに、忙しい上司に向けた資料では、数分で全体像を把握できるよう、キーメッセージだけをまとめたリストを作成しても良いでしょう。
3. サブメッセージ
サブメッセージは、キーメッセージを補強し、説得力を高めるための具体的な説明や根拠を示すものです。各スライドのキーメッセージに対して、その内容を論理的に裏付ける補足説明や理由付けの役割を果たします。
キーメッセージとサブメッセージの例として、以下のような組み合わせが挙げられます。
| キーメッセージ | サブメッセージ |
| 直近売上が好調 | 商品ごとの売上推移を見ると、XX事業が最も売上を伸ばしている |
このようにサブメッセージで、データや事実に基づく客観的な証拠を提示することで、プレゼンテーションの信頼性を高められるでしょう。
各スライドにサブメッセージを配置することで、メインメッセージとの関連性を明確にして聞き手の理解を促せます。
4. ファクト
ファクトには、デスクトップリサーチやエキスパートインタビューから得られた客観的なデータを簡潔に伝える役割があります。
複雑なデータや統計情報は、明確で読みやすいチャートを用いて表現することで、予備知識がない人に対してもわかりやすくなります。視覚的な表現を活用することで、複雑な情報や数値データを直感的に理解しやすい形で伝えられるでしょう。
表やグラフを用いる際は、重要な箇所に色や記号を加えることで、注目すべきポイントを明確に示せます。
プレゼンテーションの説得力を高めるためには、ファクトは物語の一部として組み込み、その重要性や関連性を明確に説明しましょう。
資料作成の手間を省き、パワーポイントのプロに任せたい方へ
箇条書きやメモのままでも大丈夫です。VIRTUAL PLANNERなら、まとまりきっていない情報を渡すだけでOK。専任のコンサルタントが要素を整理し、最適な構成案を作成します。
パワーポイントでプレゼン資料を作成する際の構成例5選
効果的なプレゼンテーションを作成するための代表的な構成例を5つ紹介します。
- PREP法
- SDS法
- DESC法
- 三段構成型
- 課題解決型
ひとつずつ見ていきましょう。
1. PREP法
PREP法は、Point(結論)・Reason(理由)・Example(具体例)・Point(結論の再確認)の順序で情報を整理して伝える効果的な構成手法です。それぞれの役割は、以下のとおりです。
| Point(結論) | プレゼンテーションの核となる結論や要点を明確に示す 聴衆は話の展開を予測しやすくなる |
| Reason(理由) | 結論に至った根拠や背景を論理的に説明する主張の信頼性を高める役割を果たす |
| Example(具体例) | 具体的な事例やデータを用いて理由を裏付け、説得力を強化する |
| Point(結論の再確認) | 結論を再度示すメッセージを聴衆の記憶に強く残す |
PREP法を用いると、短時間で要点を効率的に伝えるプレゼンテーション資料を作れます。
シンプルな構成であるため、話し手は論理的な展開を組み立てやすく、聞き手も内容を理解しやすいのがPREP法のメリットです。
2. SDS法
SDS法は、Summary(要点)・Details(詳細)・Summary(要点)の順で情報を伝える、シンプルで使いやすい構成手法です。それぞれの要素における役割は、以下のとおりです。
| Summary(要点) | 話の要点や概要を簡潔に伝える聴衆は後に続く詳細説明を理解しやすくなる |
| Details(詳細) | 冒頭で述べた内容の具体的な説明や裏付けとなる情報を提示するデータや事例を 用いて説得力を高める |
| Summary(要点) | 再度要点を示す聴衆の記憶に内容を定着させる |
SDS法は、ニュース番組やスピーチなどでも広く活用されており、事実を理解してもらいたい場面でとくに効果を発揮します。
単一の論点を簡潔に伝えることに適していますが、対話型のプレゼンテーションでは、相手の反応に応じた柔軟な対応が求められます。
3. DESC法
DESC法は、Describe(描写)・Express(表現)・Suggest(提案)・Choose(選択)の4つのステップで構成される問題解決型のプレゼンテーション手法です。各ステップの役割を以下にまとめました。
| Describe(描写) | 解決すべき課題や状況を客観的な事実として簡潔に伝える |
| Express(表現) | 描写した内容に対する自身の意見や考えを論理的に説明する相手の理解を深める |
| Suggest(提案) | 課題を解決するための具体的な方策を提示するこの際、命令ではなく提案として 伝えることが重要 |
| Choose(選択) | 提案が受け入れられた場合と受け入れられなかった場合の双方の結果や選択肢を示す |
DESC法は、相手の気持ちを尊重しながら要望を伝える場面で効果を発揮します。グローバル化や市場動向などの客観的事実から説明を始めることで、提案部分の説得力を高められるでしょう。
4. 三段構成型
三段構成は、序論(イントロダクション)・本論(ボディ)・結論(クロージング)から成る、プレゼン資料におけるスタンダードな構成手法です。各段階における役割は、以下のとおりです。
| 序論 | テーマや問題を提示して聴衆の関心を引きつけるインパクトのある導入やエピソードを盛り込むことが効果的 |
| 本論 | プレゼンで伝えたい内容の詳細を、データや具体例などの根拠を織り交ぜながら論理的に展開する |
| 結論 | 本論で展開した重要なポイントを要約し、行動を呼びかけて締めくくる |
三段構成型は、論文やデータ紹介など、論理的な展開が必要な場面でよく使われます。序論・本論・結論に沿って情報を整理すれば、順序立てられた流れのある資料を作成できるでしょう。
5. 課題解決型
課題解決型のプレゼンテーションは、背景から効果までを論理的に展開する構成方法です。それぞれのステップを以下にまとめました。
| 背景 | 現状とありたい姿、そしてそのギャップを明確に示すことで、聴衆との認識を共有する |
| 課題の提示 | 背景で示したギャップを深掘りする複数の課題を洗い出したうえで最も重要な課題に絞り込む |
| 解決策の提示 | 2〜3つの選択肢を示す提案内容の信頼性と説得力を高められる |
| 効果の説明 | 解決策を実施した場合の具体的な成果を明確に示す |
左右または上下の対比で課題と解決策を視覚的に表現することで、聞き手に理解を促せます。
現状からありたい姿への変化のプロセスを示すことで、納得感のあるプレゼン資料ができあがるでしょう。
「自社で資料制作する人的リソースを割けない」「クオリティが高い資料を用意したい!」という方は、弊社の資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」にぜひご相談ください!
パワーポイントで見やすい構成を組み立てるコツ
パワーポイントで見やすい構成を作るためのポイントを5つ紹介します。
- 誰に何を伝えるのかを明確にする
- 内容に漏れやダブりがないか確認する
- 複雑なデータは簡略化する
- 1枚のスライドには1つのメッセージだけを盛り込む
- 3色までに抑える
資料制作の知見を踏まえて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 誰に何を伝えるのかを明確にする
わかりやすい構成を作成するためには、まず「誰に」「何を」という点を明確にすることが最も重要です。誰に何を伝えるのかが明確でないと、主張したいことが曖昧になり、伝えたい内容が適切に伝わらない恐れがあります。
相手に応じて適切な表現を選択することも、わかりやすい構成につながる重要なポイントです。
たとえば、社内メンバー向けのビジネスプレゼンテーションであれば、専門用語や業界用語を使っても問題ありません。一方で、顧客や外部の人に向けたプレゼンテーションでは、誰にでも理解できるかんたんな言葉を選ぶ必要があります。
プレゼンテーションの良し悪しを決めるのは聞き手です。プレゼン資料は、聞き手にとって理解しやすい内容でなければなりません。
伝える相手と内容を明確化することで、最適な構成案を作成できるでしょう。
2. 内容に漏れやダブりがないか確認する
スライド資料に掲載する情報を整理するときは、漏れやダブりのない構成を心がけることが重要です。全体を要素に分けて体系的に配置する場合は、必要な情報が抜け落ちていないか確認する必要があります。
また、同じ内容を異なる表現で繰り返していないか見直すことも大切です。スライド単体の確認だけでなく、プレゼンテーション全体を通して文脈がつながっているかを確認することで、より分かりやすい構成ができあがるでしょう。
最終チェックの際には、不要な情報を削除して伝えたい内容を明確にすることで、より効果的なプレゼン資料を作れます。
3. 複雑なデータは簡略化する
複雑なデータを扱う場合は、1枚のスライドに盛り込む情報量を必要最小限に抑えることが求められます。データを視覚化するには、グラフや図表を効果的に活用し、直感的に理解できる形式で表現しましょう。
データの種類に応じて、適切な図表を選択することも重要です。
| カテゴリー比較 | 棒グラフ |
| 時系列データ | 折れ線グラフ |
| 全体に対する割合 | 円グラフ |
複雑なデータセットを扱う場合は、ひとつのスライドにひとつの重要なポイントのみを示すことで、聞き手が理解しやすくなります。
視覚的な表現を工夫することで、複雑な情報でも聴衆が素早く理解できるようなデザインになるでしょう。
4. 1枚のスライドには1つのメッセージだけを盛り込む
1枚のスライドに複数のメッセージを詰め込むことは、聞き手にとってわかりにくくなる原因です。そのため、プレゼン資料を作る際は、1枚のスライドに盛り込むメッセージは1つに絞ることが重要です。
メッセージを絞り込むことで、聞き手が注目すべきポイントが明確になり、プレゼンテーション全体の説得力が高まります。
補足説明やデータは、メインメッセージを裏付けるために必要最小限の情報のみを記載しましょう。スライド内の情報は、メインメッセージを中心に論理的なつながりを持たせることで、わかりやすいスライドを作れます。
5. 3色までに抑える
見やすいプレゼンテーション資料を作成するためには、使用する色を3色に抑えることが基本です。使用する3色は、以下の比率にすることをおすすめします。
| ベースカラー | 全体の70% | 資料全体のイメージカラーやタイトル、アイコンに使用 |
| メインカラー | 全体の25% | 要度の低いテキストやオブジェクトに使用 |
| アクセントカラー | 全体の5% | 強調したい重要な要素に使用 |
3色だけで表現することが難しい場合は、それぞれの色の濃淡を活用して使い分けても良いでしょう。ただし、最大5色までに抑えておくのが無難です。
色の数を制限することで、情報の優先順位が明確になり、聴衆が内容を理解しやすい資料ができあがるでしょう。
配色について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。
パワーポイントの構成を整えればわかりやすい資料を作成できる
効果的なプレゼン資料の作成には、明確な構成が不可欠です。資料の目的を明確にし、ターゲットに合わせた構成を選択することで、説得力が大幅に向上します。
まずは、今回紹介した基本的な構成パターンを1つ選び、次回のプレゼン資料で実践してみることから始めてみましょう。