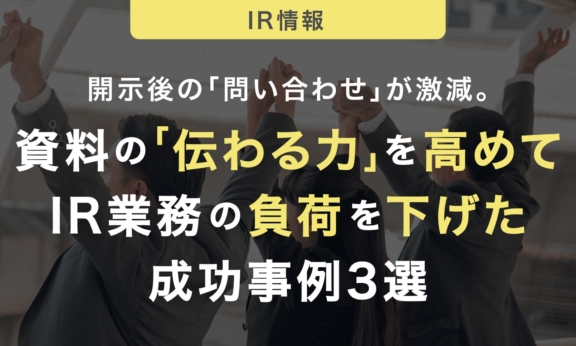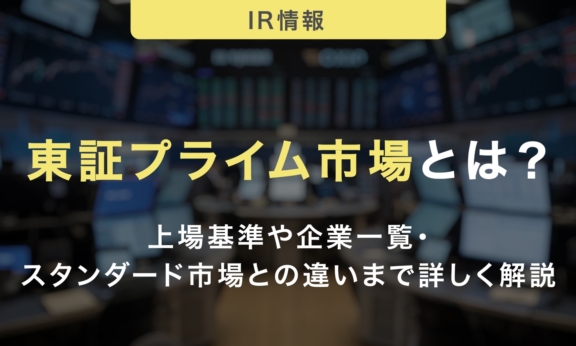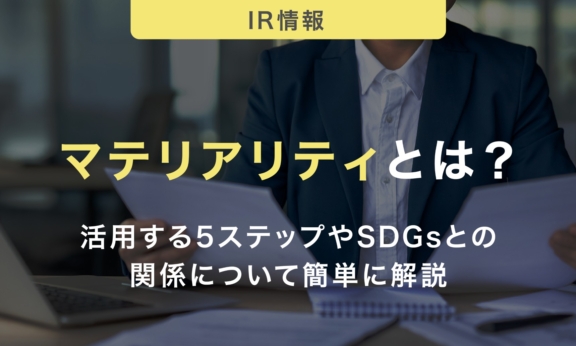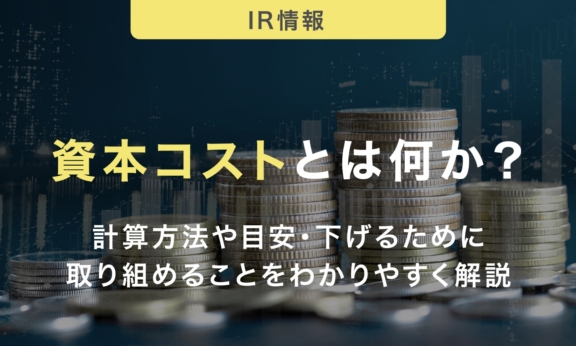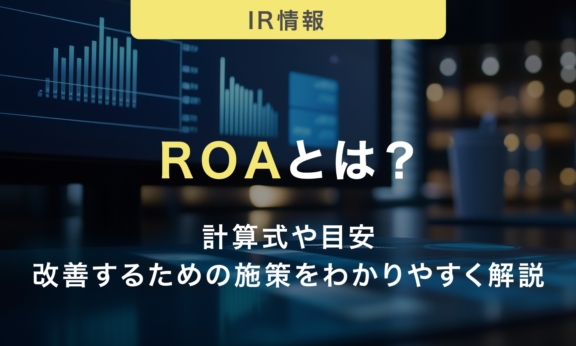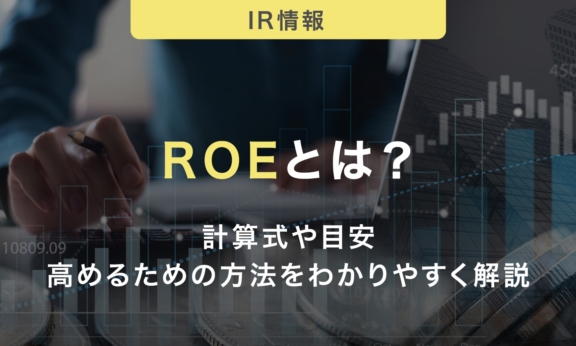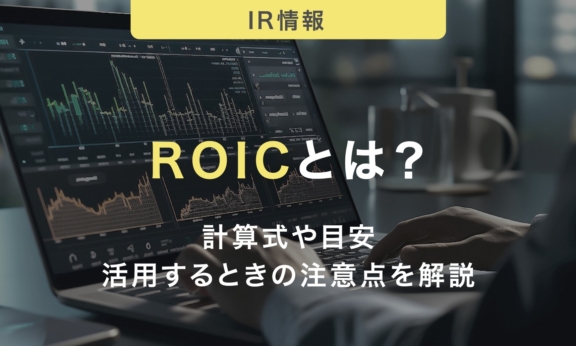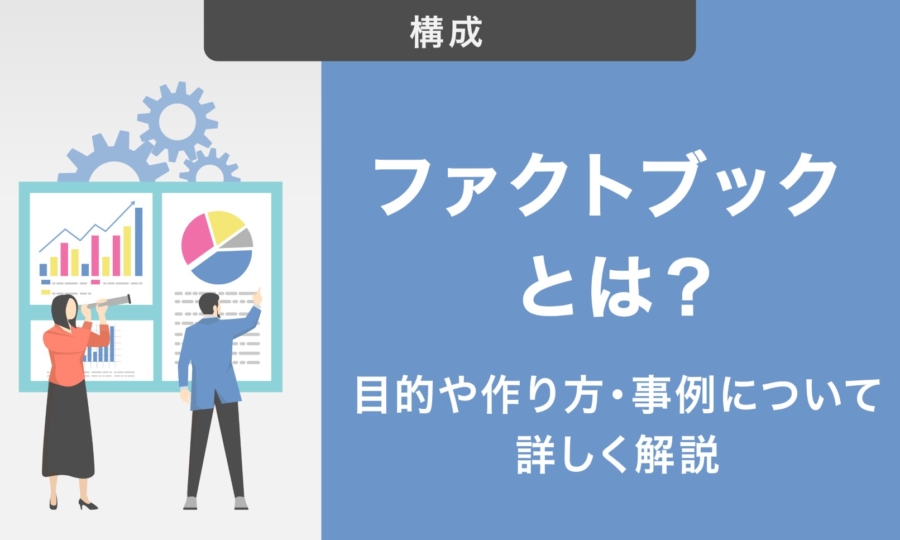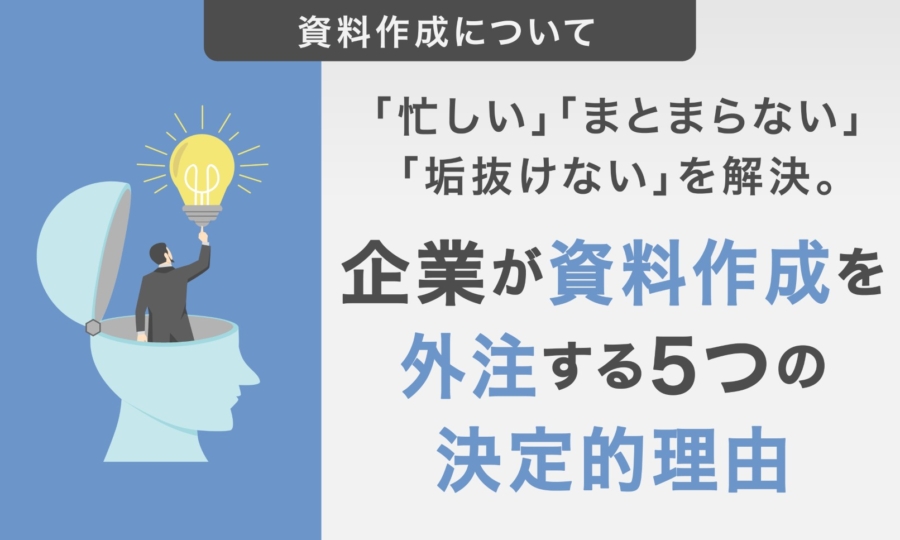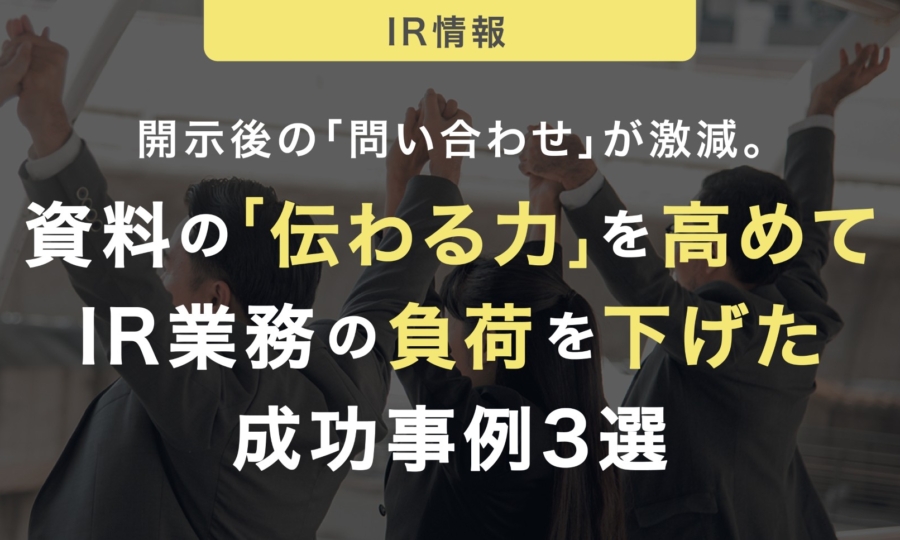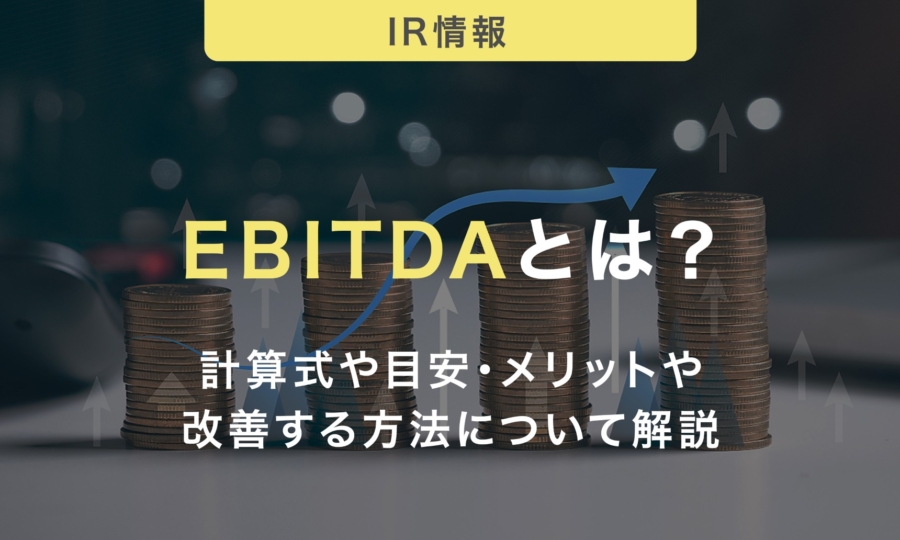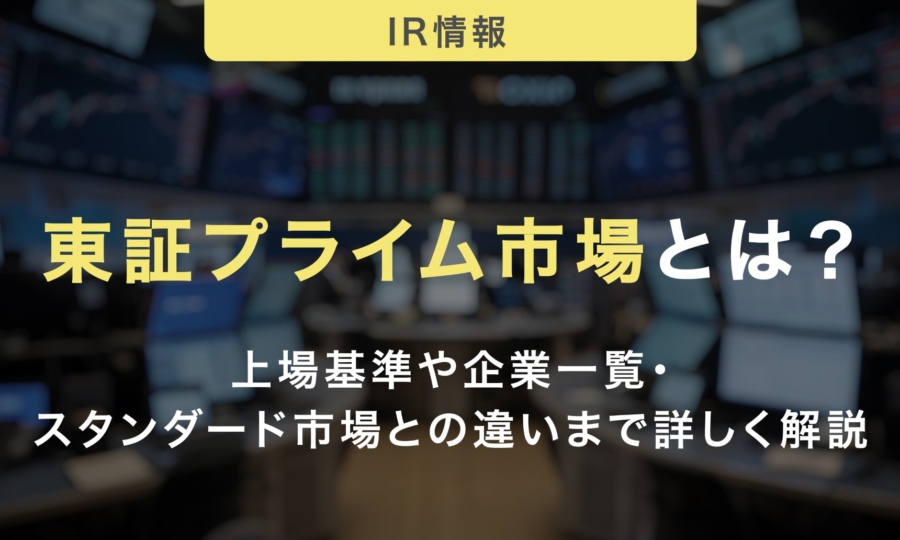EBITDAとは?計算式や目安・メリットや改善する方法についてわかりやすく解説
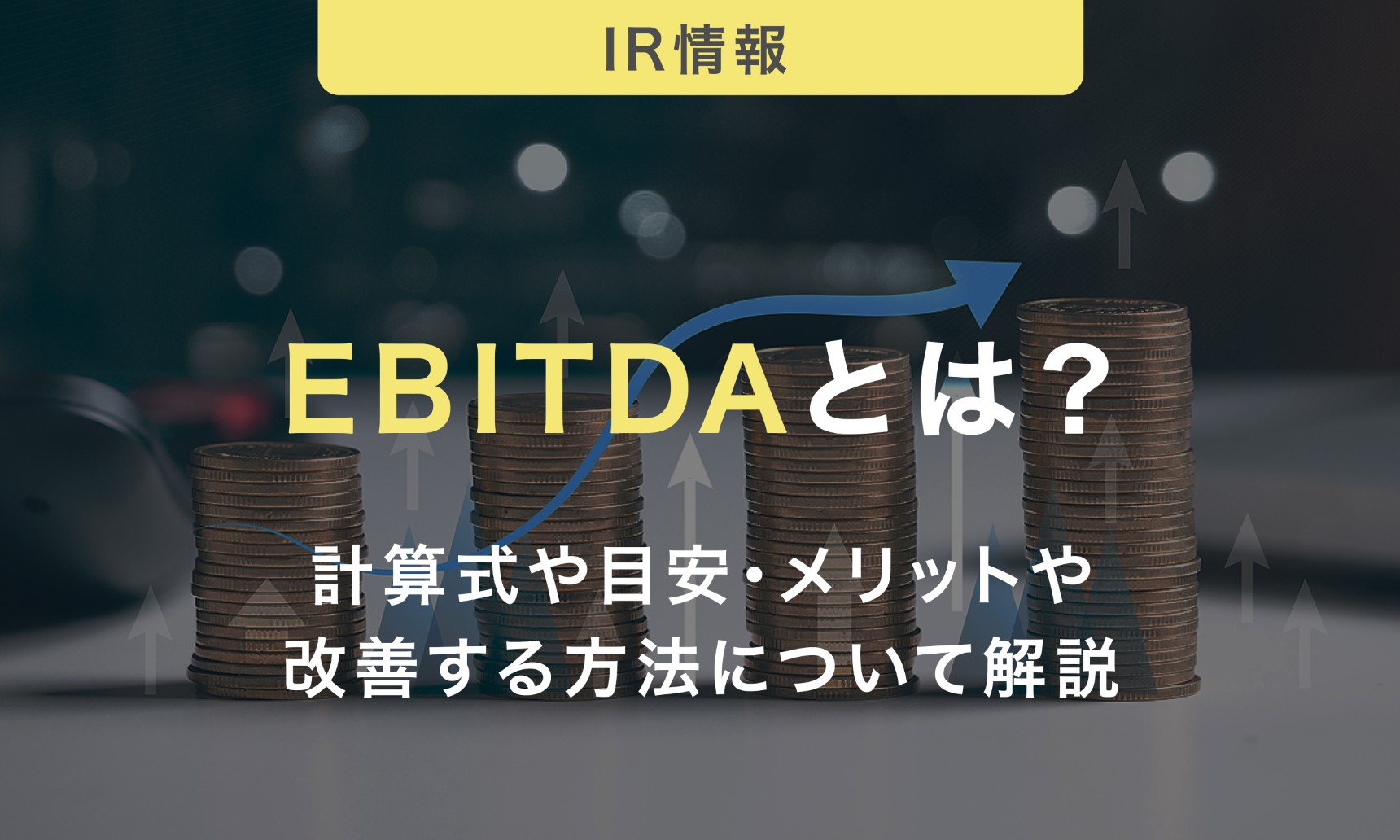
EBITDAは企業の「本当の稼ぐ力」を測る優れた物差しとして使える指標です。減価償却費や税金などさまざまな要素を除外することで、企業本来の収益力を浮き彫りにできます。
本記事では、EBITDAの基本概念や計算方法などについて、経営企画担当者や管理職の方にもわかりやすく解説します。
EBITDAを理解することで、自社の強みを正確に把握し、より効果的な経営判断や投資家へのアピールが可能になるでしょう。
複雑なIR情報を、シンプルに、分かりやすく資料化。
豊富な支援実績に基づくプロの視点で、実務担当者の負担を軽減します。
EBITDAとは?概要を解説
ここでは、EBITDAの基本的な概念について詳しく紹介します。
- EBITDAとは?
- EBITDAの計算式
- EBITDAとEBITのちがい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
EBITDAとは?
EBITDAは「Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization」の略称で、利息・税金・有形固定資産の減価償却および無形固定資産の償却を差し引く前の利益を意味します。読み方は「イービットダー」または「イービットディーエー」とされています。
主に、企業本来の事業活動でどれだけ利益を上げているかを把握するために使われる指標です。
営業利益に減価償却費やのれん償却費などを加えた数値であり、資金の流れを伴わない会計上の費用を除外することで、実際の稼ぐ力を評価できる点がEBITDAの特徴です。
のれん償却費とは…
企業の買収などで発生した「のれん(企業のブランド力や信用などの無形資産)」の価値を、会計上「無形固定資産」として一定期間規則的に分割し、費用として計上する際の費用勘定のこと。
設備投資が多い業界などでは、減価償却費が大きく変動するため、EBITDAを用いることで企業間の収益性をより公平に比較できます。
投資家や経営者が企業価値を判断する際に重視する指標のひとつであり、企業の競争力を測る物差しとして活用されています。
EBITDAの計算式
EBITDAの基本的な計算式はさまざまありますが、大まかには「営業利益+減価償却費全般」という理解で問題ありません。

営業利益に、現金の流出を伴わない費用である減価償却費などを加えることで、企業が本業で実際にどれだけキャッシュを稼いでいるかを示せます。
たとえば、製造業のように設備投資が大きい企業では、減価償却費の影響で利益が小さく見えることがあるでしょう。
その点、EBITDAを使って評価すれば、実際の稼ぐ力をより正確に評価できます。
EBITDAとEBITのちがい
EBITDAとEBITは、どちらも企業の収益力を測る指標ですが、計算の仕組みに明確なちがいがあります。
EBITは「Earnings Before Interest and Taxes」の略で、利息と税金を差し引く前の利益を示し、事業自体の儲けを表す指標です。
一方のEBITDAは、EBITに減価償却費と無形資産の償却費を加えた指標であり、実際の現金の出入りを伴わない費用を除外して算出します。
両者の関係を式にすると、以下のとおりです。
| EBITDA = EBIT + 減価償却費全般 |
ここでは、年間売上高1億円の企業が以下の費用を持つ場合を考えてみましょう。
| 年間売上高 | 1億円 |
| 材料費・人件費など | 6,000万円 |
| 減価償却費全般 (のれん償却費等含む) | 1,500万円 |
| 支払利息 | 300万円 |
| 法人税 | 800万円 |
このような条件の場合、EBITとEBITDAは以下のように計算できます。
| EBIT=売上高 – 材料費・人件費など – 減価償却費全般 = 1億円 – 6,000万円 – 1,500万円 = 2500万円 |
| EBITDA = EBIT + 減価償却費全般 = 2,500万円 + 1,500万円 = 4000万円 |
つまり、EBITは会計上の利益、EBITDAは実質的なキャッシュ創出力に焦点を当てた数値といえます。
EBITDAの目安
EBITDAの目安を考える際には、EBITDA単体の数値ではなく「EV/EBITDA倍率」という指標で評価するのが一般的です。この数値は、企業価値(EV)がEBITDAの何倍にあたるかを示すもので、M&Aなどの企業価値評価で多く用いられます。
この倍率が低いほど、投資コストを短期間で回収できる「割安」な企業とされます。
EV/EBITDA倍率の平均的な水準は8〜10倍程度といわれており、製造業やIT業界など、資産構造や利益率の異なる業種によって適正倍率は変動します。また、中小企業では3〜5倍が目安とされることもあります。
EBITDAは、企業の現金創出力を測る尺度であるため、数値の大小よりも同業他社との比較や過去の推移を踏まえて判断することが重要です。
EBITDAを指標とするメリット
EBITDAを指標として使用するメリットには、以下の3つがあります。
- 本業の収益力を正確に把握できる
- グローバル企業と収益力を比較できる
- 設備投資の影響を排除できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
本業の収益力を正確に把握できる
EBITDAを指標として用いる最大のメリットは、企業の本業による収益力をより正確に捉えられる点にあります。
営業利益では、減価償却費やのれん償却費といった費用が差し引かれるため、実際の事業活動で稼いだキャッシュの量を正しく反映できません。
その点、EBITDAなら減価償却費全般を加算して算出するため、企業が日々の営業活動でどれだけの現金を生み出しているかを評価できます。また、設備投資の時期や規模の違いに左右されにくく、事業構造の異なる企業間でも公平な比較が可能です。
そのため、製造業やインフラ業のように投資額が大きい業種では、EBITDAを使うことでより実態に近い経営の収益性を把握できます。
グローバル企業と収益力を比較できる
EBITDAを使う大きな利点のひとつは、国や企業規模を超えて収益力を比較できる点です。
各国では税制や金利水準・減価償却の方法などが異なるため、当期純利益や営業利益では優劣を正確に比較することは難しいでしょう。
EBITDAを使えば、利息や税金・減価償却といった要素を除外して算出するため、会計制度や資本構成のちがいに左右されず、企業本来の事業収益力を評価できます。たとえば、アメリカ企業と日本企業のように制度が異なる企業間でも、同一の基準で比較できるということです。
さらに、EBITDAマージン(EBITDAを売上高で割った比率)を用いれば、規模の異なる企業同士でも効率的な収益構造を相対的に評価できます。このような点から、EBITDAはグローバル経営や国際投資の共通言語といえるでしょう。
設備投資の影響を排除できる
EBITDAを指標として活用すれば、企業は設備投資の影響を排除したうえで本業の収益性を評価できます。
そのため、投資の時期や規模に左右されず、企業が事業活動からどれだけ安定してキャッシュを生み出しているかを判断しやすくなります。
製造業や通信業のような大規模な設備投資が不可欠な業界では、EBITDAを用いて評価することで設備更新のサイクルによる利益のブレを抑え、収益力を正確に比較できるでしょう。
EBITDAを指標とするデメリット
EBITDAには多くのメリットがありますが、以下の3つのデメリットにも注意が必要です。
- 実際のキャッシュフローを正確に反映できない
- 過剰な設備投資を見抜けない
- 経営の健全性を過大評価する恐れがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
実際のキャッシュフローを正確に反映できない
EBITDAは、企業の収益力を示す便利な指標ですが、実際のキャッシュフローを正確に表しているわけではありません。
EBITDAには、利息や税金・運転資本の変動・設備投資などの企業経営における現金の出入りが考慮されていないためです。
つまり、EBITDAが高くても、実際には設備投資に多額の資金を使ってキャッシュが不足していることもありえます。
実際の資金の流れを正確に把握するには、営業キャッシュフローやフリーキャッシュフロー(FCF)を併用して確認する必要があります。
EBITDAはあくまで理論上の「稼ぐ力」を示す指標であり「手元に残る現金」を保証するものではないことは押さえておきましょう。
過剰な設備投資を見抜けない
EBITDAを使う際の注意点として、過剰な設備投資を見抜けないことが挙げられます。EBITDAは減価償却費を加え戻して利益を計算する指標であり、設備投資によって生じた費用の影響を除外するためです。
そのため、本来は投資過多で企業の資金繰りを圧迫していても、数字上は安定した収益を上げているように見えることがあります。
とくに、資本集約型の業種では巨額の設備更新や新設が続くと、将来的なリターンが不確実なまま多額の支出が発生し、経営の持続性を損なうリスクが高まります。
設備投資の適正さを見極めるには、キャッシュフロー計算書やROICなど、ほかの指標と併用する必要があります。
ROICについて詳しく知りたい方は「ROICとは?計算式や目安・活用するときの注意点についてわかりやすく解説」の記事を参考にしてみてください。
経営の健全性を過大評価する恐れがある
EBITDAを重視しすぎると、経営の健全性を実際より高く評価してしまう恐れがあります。
EBITDAは、利息や税金・減価償却を除いた「稼ぐ力」を示しますが、企業の資金繰りや財務状況に直結する重要な要素が含まれていません。
そのため、借入金が多く利払い負担の重い企業でも、EBITDAが高ければ健全に見えてしまいます。また、設備の老朽化や維持コストなど、将来的な支出リスクを反映できない点も見落としてはいけません。
とくに、資本集約型の業界では、減価償却を除外することで投資負担の大きさが隠れ、実態よりも高い利益水準に見えることがあります。
そのため、財務健全性を正確に測るには負債比率やキャッシュフローなど、ほかの指標とあわせて分析する必要があるでしょう。
EBITDAを改善する方法
EBITDAを改善するための方法として、以下の3つの手法が効果的です。
- 売上高を増加させる
- 負債を削減して財務改善を図る
- M&Aを活用する
ひとつずつ解説します。
売上高を増加させる
EBITDAを改善する最も基本的な施策は、売上高を増やすことです。売上が増えれば営業利益が上昇し、それに伴いEBITDAの数値も向上します。
具体的には、新規顧客の獲得や既存顧客のリピート率向上を目的としたマーケティング施策の強化が有効です。また、商品やサービスの価格戦略を見直し、付加価値を高めることで単価を上げる取り組みも効果的です。
また、品質改善やアフターサービスを充実させることによって顧客満足度を高めれば、価格競争に巻き込まれることなく収益性を維持できるでしょう。
負債を削減して財務改善を図る
EBITDAを改善するには、負債を削減して財務基盤を強化することが効果的です。借入金を減らせば支払利息の負担が軽減され、財務コストが減ることで企業全体の利益体質が改善します。
すると、間接的にEBITDAやキャッシュフローの改善につながる可能性があります。実質的な借入金を縮小するために、余剰資金を活用した返済や不採算資産の売却などを進めることが有効です。
財務負担を軽くすることで、経営の安定性と投資余力を高め、企業価値の向上にもつながるでしょう。
M&Aを活用する
M&Aを活用することは、EBITDAを向上させる効果的な手段のひとつです。企業買収や統合を通じて、事業規模の拡大やシナジー効果を得ることで売上や収益性を高められます。
また、重複するコスト構造や業務を整理・統合することで、経費の圧縮や効率化も進みます。EBITDAは、利息や税金・減価償却といった要素を除外して算出されるため、M&A後の純粋な事業収益力を把握するうえで有効です。
実際には、収益基盤の強化だけでなく、非効率な子会社の整理や不採算事業からの撤退を通じて、持続的な収益体質への転換を図るための戦略的手段としてM&Aを位置づける企業も増えています。
EBITDAは本業の稼ぐ力を測る指標
EBITDAは、企業の本質的な収益力を示す重要な指標です。会計処理や財務構造のちがいを排除して、純粋な事業活動による収益力を可視化できます。
EBITDAを活用すれば、設備投資の時期による利益変動に左右されない経営判断が可能になります。同業他社との比較やM&A評価などさまざまな場面で活用し、企業価値向上のための戦略立案に役立てましょう。